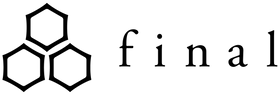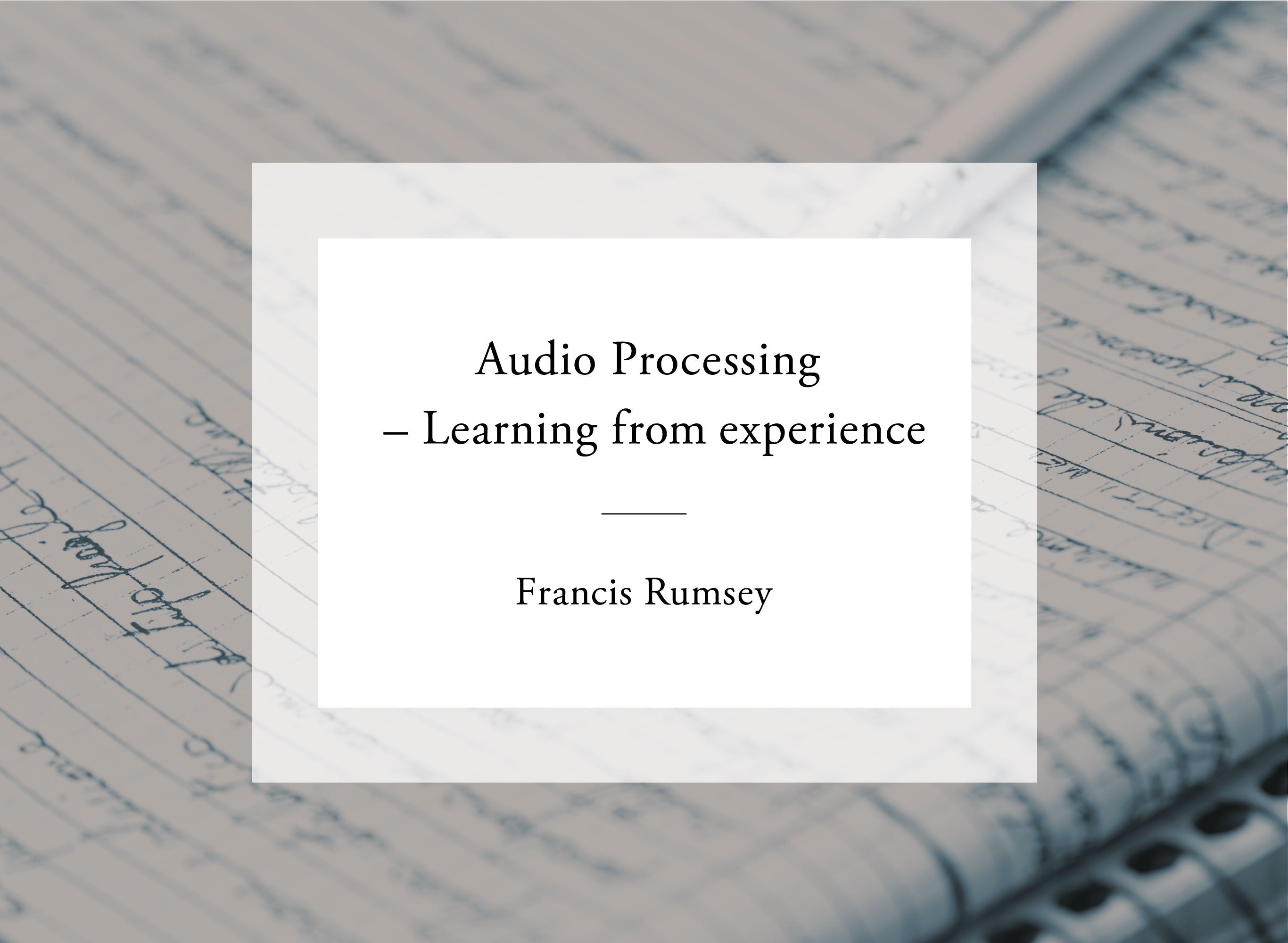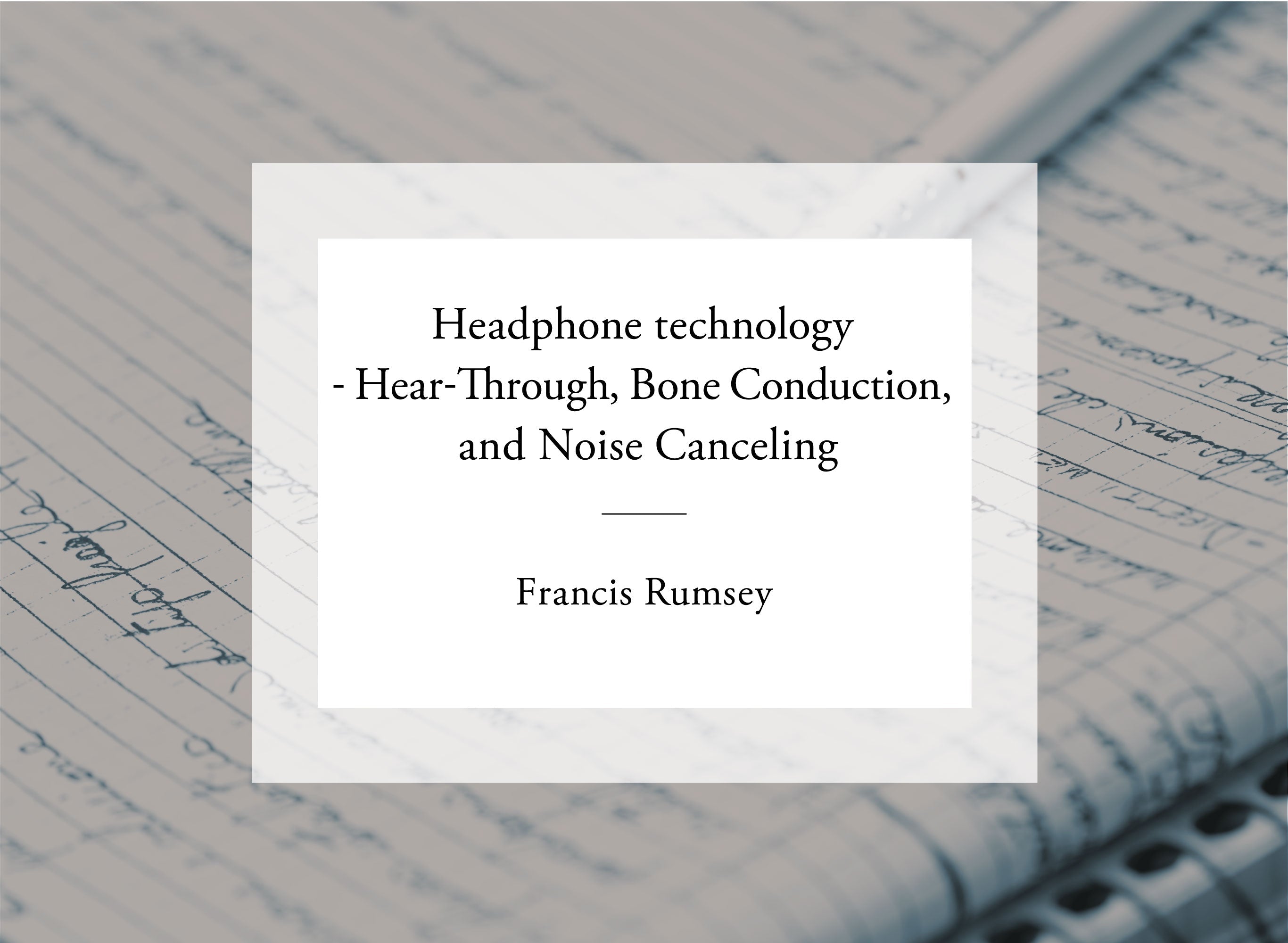音に関連した多様な分野で活躍される方々をお招きし、弊社チーフサイエンティストの濱﨑が、「音」についての様々なテーマについてお話を伺う企画です。 第1回目は、現在finalが共同研究を行なっている、九州大学大学院芸術工学研究院の河原一彦博士にお話を伺いました。お話しいただいたそのままを文章にしましたので、読みにくいところがあるかとは思いますが、これによって、文章から話し手の言葉そのものを感じ取っていただけることと思います。 4時間ほど伺ったお話を、主たる項目に分けてお伝えします。パート5は『聴能形成とは』です。
九州大学大学院芸術工学研究院 河原一彦博士
・聴能形成とは
・聴能形成とは
九州大学芸術工学部聴能形成教室
九州大学芸術工学部聴能形成教室
九州大学芸術工学部聴能形成教室
九州大学芸術工学部聴能形成教室
濱﨑:聴能形成については、先ほど先生の方からも開学以来、授業でもやってきた取り組みということですので、少し詳しく紹介してください。まず聴能形成とは何ぞやということから始めて、今、どのようなことを目指してやっていらっしゃるかみたいなことを含め、ご紹介ください。お願いします。
河原:聴能形成というのは、音の聴覚印象、聴いた感じですね、聴こえと音響物理指標の対応を身に付けると、まず。それによって、音に関する感性を育てる音響技術者のための総合的なカリキュラムというふうに謳っています。キーワードは、とりあえず音響技術者のための総合的なカリキュラムですね。音の聴こえと物理的な性質という所の対応を身に付けるということが大事です。九大の音響設計では、1年次に開設しています。一昨年までは、1年生の前期に開講していましたけれども、改組があったので、1年生の後期ですね、去年の後期から、1年生でやっています。おそらく1年生は、別のキャンパスで授業を受けているので、僕らは機材を運んでいくわけですけれども、もしかしたら、その年の後期には、その授業が、聴能形成だけが対面の授業だったんじゃないかっていう噂ですけれども。あまり、まだ2年生としっかり話をしていないので分かりませんが、今の現2年生と対面でやりました。これには色々理由があるわけですけれども。聴能形成、特に1年生の時は、いきなり音を聴くというだけじゃなくて、音圧とか音圧レベルとか周波数とかスペクトルとか、そういうことをかみ砕いて授業・講義をした上で、座学というか、講義ですね、講義と合わせて訓練を行いますと。アンケートとかレポートを見ていると、音響に入った実感というか、音響設計コースに入った実感みたいなものを感じてもらえる授業みたいで、割と楽しんで受けてもらって、というか、楽しんでもらえるようなカリキュラムを作っていますけれども、まずは、音を聴くということに対して、きちんとやってくださいということです。
濱﨑:初学者、1年次から訓練を行うというのは、実質、訓練の期間としては、どれくらいですか。
河原:半年ですね。15回ですね。15週ですね。
濱﨑:以前に比べると、減ったんですね。私の頃は、2年間やっていました。
河原:現在は、聴能形成Iが半年、聴能形成IIが半年で、合計1年間です。僕自身も学生の時は、聴能形成Iが1年生の時に通年であって。2年生の時に通年で聴能形成IIがあって、合計2年間でしたね。
濱﨑:あと、アイデンティティという所で言うと、例えばソルフェージュとか、あるいは、ピアノの演奏が必須だったりとか、普通の工学部ではやらないようなことを今もやっていらっしゃるんですか。
河原:そうですね。ソルフェージュはなくなったんですけど、ピアノは、やっています。それから、音楽理論の授業もやっていますけど。そういうピアノのレッスンだったり、音楽の授業というのが、2年生以降にしか開講できないんですね。そうすると、1年生は自分が音響設計に入ったというのを実感できる授業は、後期の聴能形成Iしかないんです。そこは、入ったかいがあっただろうと思ってもらえるような授業をした方が良いと思っていて、僕は。なので、手間がかかりますけど、機材を毎回運んで、設置・調整。調整までは、しないかな。でも音圧レベルくらいは、試験音源で確認してみたいなのは、していますね。そうしないと、2年生になるモチベーションとか、2年生の専門とのつなぎの部分で講義を上手くやって。音圧、音の大きさというか、元々パスカルだけのを、それをデシベルに直して。10デシベル5デシベルに近いのはどんな感じとか、1キロヘルツの純音はどんな感じ、1キロヘルツのバンドノイズはどんな感じ、1キロヘルツの山付けはどんな感じみたいなものを分かるようになった自分というのは、レポートとかに書かせても、トレーニングしたら聴き分けられるようになるっていうことの喜びというか、そういうのに溢れたようなレポート、そういう自信を持ってくれているっていうようなレポートとか感想が多いので、やって良かったのかなと思っています。2年生では、もう少し品質とかいうのに関係しているような訓練をやるので、高田先生メインですけど。あとは、品質の中でもありますけど、デジタル信号の量子化ビット数を変えた音源とか、そういう量子化ノイズを聴き分けるような訓練と併せて、次に習うデジタル信号処理の橋渡し的な訓練を入れたりとかしています。僕自身、芸術工学部の同窓会とも関係していて、卒業生と色々な話をしていても、聴能形成、あるのが当たり前に僕らは、なっているんですけど。それによって、品質なり音の特徴を曖昧さなく伝えることができるという所が、聴能形成のインパクトだろうと思っていますね。なので、A社とB社で協業するような時に、間に芸工の出身者がいると、音の品質をきちんと伝え合えるというか、単に音響出身だからというのではなくて、そのバックボーン、背景には、基盤には、聴能形成があって、それを元に、音の品質を物理的に説明しているというようなことがあるなというふうに感じて、自分なりにまとめながら取り組んでいるところです。
濱﨑:ありがとうございます。それでは、聴能形成について詳しく説明していただけますか。
河原:聴能形成って、やみくもにトレーニングするわけじゃなくて。聴能形成の学習フェーズって、これ岩宮先生とまとめたんですが。音、まず聴き比べて違いが分かるっていうフェーズですね。違う音が違うって分かるとか、同じ音が同じって分かるっていうことをまずやります。物理的なものと関連付ける前に、同じ音とか違う音、何が違うかとか。例えば周波数を変える時に、どういうふうに自分は感じるかみたいなものをきちんと把握させています。これ、シーショアテストって、シーショア(Carl Emil Seashore)という音楽音響の古典みたいな研究者の方が、SPレコードで提案しているトレーニングなんですけど。トレーニングというよりは、これ訓練しても、あまり分かるようになるというより、僕らの位置付けとしては、音を集中して聴く練習っていうふうに感じています、位置付けています。なので、こういう簡単なタスクから始めて、音の違いが分かると。その次に、違いを、物理的なパラメータの違いとして認識できると。例えば、10デシベル違う音の大きさだとか、何ヘルツの純音なのかとか、そういうのを聴き分けられるようにする。これが聴能形成の主たる部分ですね。岩宮先生が付け足して解釈されているんですけど、こういう音の違いを物理的なパラメータとして認識できるようになると、何ヘルツの音とか、何デシベル小さい音とかという物理量を与えられると、その音をイメージできるようになります。これが例えばグラフを見て、論文とか調査結果のグラフを見て、こういう音なんだなってイメージできるとか、そういう所の大事な能力ができる。想像力の部分は、実際にトレーニングはできていないんですけども、想像力が付くっていうのは、みんなの共通体験として持たれています。僕が提案しているのは、みんなでやると想像力を共有できるので、音のイメージを共有することができるというふうに考えています。なので、さっき言ったみたいに、音響の卒業生同士が違う会社にいて協業する時に、イメージをきちんと共有する時に、擬音語を使わずに物理量を使って、音の音質なり品質なりを共有することができるっていうのが、聴能形成のインパクトがある所ですね。なので、こういう活動を通じて、ぜひ広めていきたい所ではあります。
濱﨑:今、お話があった物理量からどうイメージするという物理量としては、周波数と、それから音圧と帯域スペクトルですね。そのほかには、例えばひずみ率などの物理量がありますね。あるいは、両耳聴で言えば音の方向とか、あるいは残響時間とかですか。
河原:残響時間は、やっています。ひずみなんですけど、よく言われる、指摘されるんですけど、指摘というか、提案されるんですけど。これなんか考えていくと、ひずみ、この音は何パーセントのひずみだというのを当てることはできるかもしれないですけど。ひずみって、色々なひずみがあって、ひずみ率という数値だけでは表せないので、そこが困っている所ですね。そこで、ひずみの訓練として、僕が頑張って量子化のビット数というのを考えました。それで、量子化ビット数も実はビットレートの方が良いんじゃないか、伝送のビットレートの方が良いんじゃないかなっていう意見とかもあって、実際に、そういう訓練をされている所もあるんですけど、例えばMP3だと、エンコーダーの性能によって、ビットレートが意味をなさなくなってしまって、リファレンスのエンコーダーっていうのがないというか、事実上あるのは、AppleのiTunesがMP3の規格の策定中のアルゴリズムを使っているので、それが良いんじゃないかとかいう話をしているうちに、MP3が使われなくなってしまって、あまり意味がなくなってしまったというので、困っています。ビットレートとひずみ率、ひずみは、僕も体験させたいなと思っている項目の1つで、あるひずみ方に限って何かやってみるとか、もしくは、クリップみたいなひずみと何種類かのひずみを混ぜて選択・回答させるとか、そういうのをできないかなと考えていて、時間の取れる時に音源を作ってみようかなと思っているところです。ラウドネスが変わらないようにしないといけないので、そこが、手がかかります。今も周波数特性の山付け判定とかも、実はラウドネスを揃えているので、1キロヘルツ2キロヘルツは音が大きく聴こえるとか、そういうのが手がかりにならないように、より難しくなっているんです。
濱﨑:ありがとうございます。聴能形成というのが、音響技術者、つまり、生業として、あるいは、仕事として音を扱う人たちのための職業訓練的な意味合いですよね。一方で、先ほど聴能形成を経験した者同士は、音を表現するのをいわゆる印象語ではなくて、物理的な用語、例えば、この音は1 kHzあたりに2dBのピークがありますねとか。そういうことをすると、たちどころにお互いに問題意識をきちっと共通化できると。一方で、民生用オーディオって言うんですか、趣味のオーディオ、例えばこのイヤホンは、10 kHzくらいピークがありますねとか話している人たちもいますが、多くは、色々な言葉で、その音の意味を、印象を表す。でも、その言葉が同じでも、本当にその人が言っていることと、自分が感じていることが一緒かどうかも分からない。その問題というのは、趣味だからそれはそれでいいのか。何かそういう、より客観性を持たせたような会話がオーディオを楽しむ人たちにもできていくと、良い方向になるのか。その辺りは、どうですか?
河原:僕は、オーディオを楽しむためのリテラシーみたいなものとして、聴能形成。聴能形成のスコアが高いからオーディオを楽しめるっていうことではないかもしれないですけど、聴能形成をある程度行った人で、オーディオを楽しみながら評価してもらったらいいのかなと思っています。オーディオに関わらず、音楽もソルフェージュみたいな意味合いというか、音を聴く職業というか、行為をする人のたしなみというか、1つの目標みたいな感じで聴能形成の認証というかスコアを取ってもらうっていうのは、将来的にやれると良いかな、やったら良いかなと思うし。音を聴く行為に、物理的な裏付けがある状態で行ってもらえれば、評価の指標が、責任というか、きちんとした評価ができるし、物理的な用語で正確に表現してもらえるようになるだろう。そういうふうになると、音に関する産業の健全な発展というか、そういうのができるんじゃないかなと思っています。なので、大学に籍を置いているうちに、もう少し頑張って、聴能形成検定とかできたら、技能検定みたいな感じで、一般の方もというか、生業としない方も受けてもらえるように将来的にできたら、日本人の音の聴き方自体が、良い方向に変わってもらったらいいかなと思っているんですけどね。日本語って、擬音語っていうすごく便利なものがあるので、その表裏一体でしょうね。擬音語を使って共有できちゃうから、物理量を表さなくてもよかったんだけど、擬音語から連想される品質というのが、個々人によって違ったりしているので、そうじゃない状態にすると、産業的にはすごく有効じゃないかなって考えています。
濱﨑:擬音語というのも、ある意味自分の印象をどういうふうにして言葉で表そうかっていう、楽しいことでもありますよね。おそらく、新しい言葉を作っていくっていうのは、若い人たちは大好きで、次から次に、新しい言葉が生まれていますよね。20年前、オーディオを好きな人たちが使っていた擬音語と、今、まさしくイヤホンとかヘッドホンを主体として聴いているオーディオで音楽のファンが使っている擬音語では変わってきている。自分が独特の表現をするということに対して、喜びもありますよね。だから、それを物理的に表現しなさいと強制すると、楽しみを奪ってしまう。ただ、相手に正確に伝えるには、例えばこういった少し物理的な表現もできるようなことを、訓練でもないですけど、そういった経験をするっていうことが普通の人でもできれば、興味を持つ人は間違いなくいると思いますけどね。
河原:なので、もうちょっと、2、30年前から聴能形成を普及させるには、どうしたら良いのかみたいな話は、じんわりあったんですけど、特に産業界は、割と急いでやらないといけない感じになってきているみたいなので、僕も動ける時に動いてみようかなと思っています。例えば能力検定を実施した時に、オクターブ間隔の周波数のイメージを持っていますよと、5dBか2dBとか3dBとか、音圧レベルの違いというのはどれだけのものか分かっていますよっていう前提でミーティングするのと、そうでないのっていうのは、全然違うと思うので、その辺産業界の要望を上手く取り込みながら、みんながハッピーになるような広め方というのをやりたいですね。おそらく、音の違いに気づくとかいうようなことも、実は語学教育とか、そういう所にもつながるような気がして。今、文科省とかもリスニングを重視するような話が出ているので、いきなり英文を聞くんじゃなくて、英語を聞くんじゃなくて、音が違うか同じかっていうのを聞き分けるとか、そういうシーショアテストみたいなことをやることによって、何に注目して聞いたら良いのかっていうことを体感していくというのは、1つ聴能形成のあり方としては、ありえるんじゃないかなと思っています。
濱﨑:今、語学の話が出ましたけれども、これ私の個人的な経験だけでしかないかもしれないですけど、でも同じようなことを皆さんおっしゃる。語学というのは、基本的にはしゃべることと聞くことで、特にヒアリングの方は、リニアに上がっていかないんですよね。ある時、急にサッと聞こえて、理解できるようになる。また、そうすると壁ができて、またしばらく聞くと、少し階段状に自分のヒアリングする能力が上がるような感じを受けるんですけれども。聴能形成を訓練、例えば1年生で入ってきて、今まで、それこそ音の物理のことも知らない、dBも初めて、周波数1 kHzというものを想像できないような人たちが、弁別という意味で、語学学習と同じくリニアに上がらずに、ある時サッと少し視界が開けたように聞こえるような、そういう上達の仕方をしていくんですかね。それとも、日々だんだん上がっていくんですか?
河原:個人の細かい所を十分分析できているわけじゃないんですけど、回答状況を見ていると、聞きどころが分かったと思うトレーニングの節目があるみたいで、そうすると、スルスルッとある日を境に聞き分けられるようになったみたいな。先ほど、濱﨑さんがおっしゃったみたいに、ある時に理解できたとか。僕は、周波数特性の山付けみたいな訓練だったんですね、例えばギターの音に注目して聴きなさいとか、ドラムの音色に注目してみなさいみたいなことを僕から言わないようにしていて、1回トレーニングした後に、スコアの良かった人にインタビューというか、君の聴きどころを教えてくださいみたいな、何人かに言わせてみるようにしたんですね。そうすると、誰々君はこう言ってたとか、誰々君はこういうふうに言ってたというのを参考に次のトレーニングに向かってもらうと、そうすると、聴き分けられたっていうのもあって。僕は、特定の聴き方を強制しない代わりに、聴きどころの共有というのは、時々行うようにしています。そうすると、自発的に、自分は、違う所を手がかりにしたっていうのも、もちろんいいので、参考にしてくださいっていうのは、割と好評みたいですね。なので、聴きどころの共有とか、EQのトレーニングの特徴かもしれませんけど、音色が変わって聴こえるので、そのトレーニングの音源がどういうふうに聴こえたかというのを共有し合うことっていうのは、聴能形成の次のステップにつながるかなと。個人の能力を上げるんじゃなくて、集団の能力を上げるという時に、とても有効なやり方かなと思っています。ただ単に訓練をするだけじゃなくて、聴いた感じというのをゴニョゴニョってみんなで話し合わせてみるというのは、割と大事なことだなと思っています。
濱﨑:聴能形成、職業訓練という観点からすると、音を生業とされている会社で、複数の会社が実際会社の中の訓練としてやってらっしゃいますよね。他の大学でも同じ、カリキュラムの中身は違うかもしれないですけど、聴能形成をやっているような芸術系の大学などありますね。その辺りは、全体の仕組みというんですか、聴能形成の訓練のやり方みたいな所は、河原先生がその都度、監修されているみたいなことが、現状としては、そうなんですか?
河原:企業で導入される場合は、割とご相談いただいているという例が多いですね。大学の場合は、ここのOBの方が持ち帰ってというか、実践されているようなので、大体カリキュラムについては、あまり相談されることはないんですけれども、その時に得られる、使える機材的な資源にもよりますね。企業さんの場合は、割と深刻な事情がある場合もあって。ある会社の場合だと、音響機器にしても、開発がコンピュータベースで、コンピュータで開発できちゃって、設計というか、作図してボタンを押すと、周波数特性が見えちゃう、計算できちゃうと。その会社の偉い方が「最近心配なんだよね。みんなパソコンに向かってグラフを見ているけど。あれで大丈夫なのかな?」っておっしゃっていて。九大に調査に来られて、聴能形成のデモをしたら、「これだ。うちの会社に必要なのは。これを全社でやろう」みたいなことで、トップダウンで導入されたような事例もあります。その時は、割と長期にわたってカリキュラムを整理しながら、初級編・中級編・上級編みたいなもののロードマップを作って、ちょっとずつ導入したりとかしたような事例もあります。地元のベンチャー企業さんのお手伝いをしていた時に、聴能形成を社内でやったら、そこの社長さんに言われたのが、工場の開発とかのスタッフの間の、それから、営業の方とのコミュニケーションが、すごく良くなりましたとおっしゃったのが印象に残っていて。やっぱりトレーニングをすると、お互いの言ってることが分かり合えるきっかけになるんだなと思ったのが、僕が先ほど、ここに書いているような関連技術者とかに広げたりとか、音を聴く基盤になりえるというようなことを思いついたというか、確信したきっかけですね。聴き分けられるようになったと思うと、とてもエンジニアの言ってることが分かるし、エンジニアも、物理量ベースで話してもらうと、受け止めようもあるわけですね。だから、そういう所が大事なのかな、聴能形成の効果としてあるのかなって思いました。
濱﨑:多分これをやった卒業生、聴能形成から、さらに例えば音を扱う現場によっては、ものすごくより精度の高いことを求められながら、オン・ザ・ジョブトレーニングみたいなのをして、さらに、能力を研ぎ澄ましていくんでしょうけれども。やっぱり、そういうことを経験した立場から言うと、印象表現だけでコミュニケーションをするというのは、正直結構厳しいですよね。分かろうとするんですけど、本当に自分が相手の言ってることを理解できているかどうかという不安がずっとつきまとう。
河原:そういう意味じゃ、実はオーディオの業界じゃないんですけれども、機械系の業界では、割と聴能形成、オーディオじゃない業界でも、音とか騒音とかに関係する業界が実は、あって、そういう人たちも、こういう訓練と、例えば認証、検定ですね、そういうのを作ってもらえないだろうかって、音の聴き分け能力とかいうような言い方もされているみたいですね。注目されているうちに進めないと。
>>続きを読む:Vol.1-6 『音響教育と民生オーディオ』