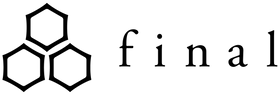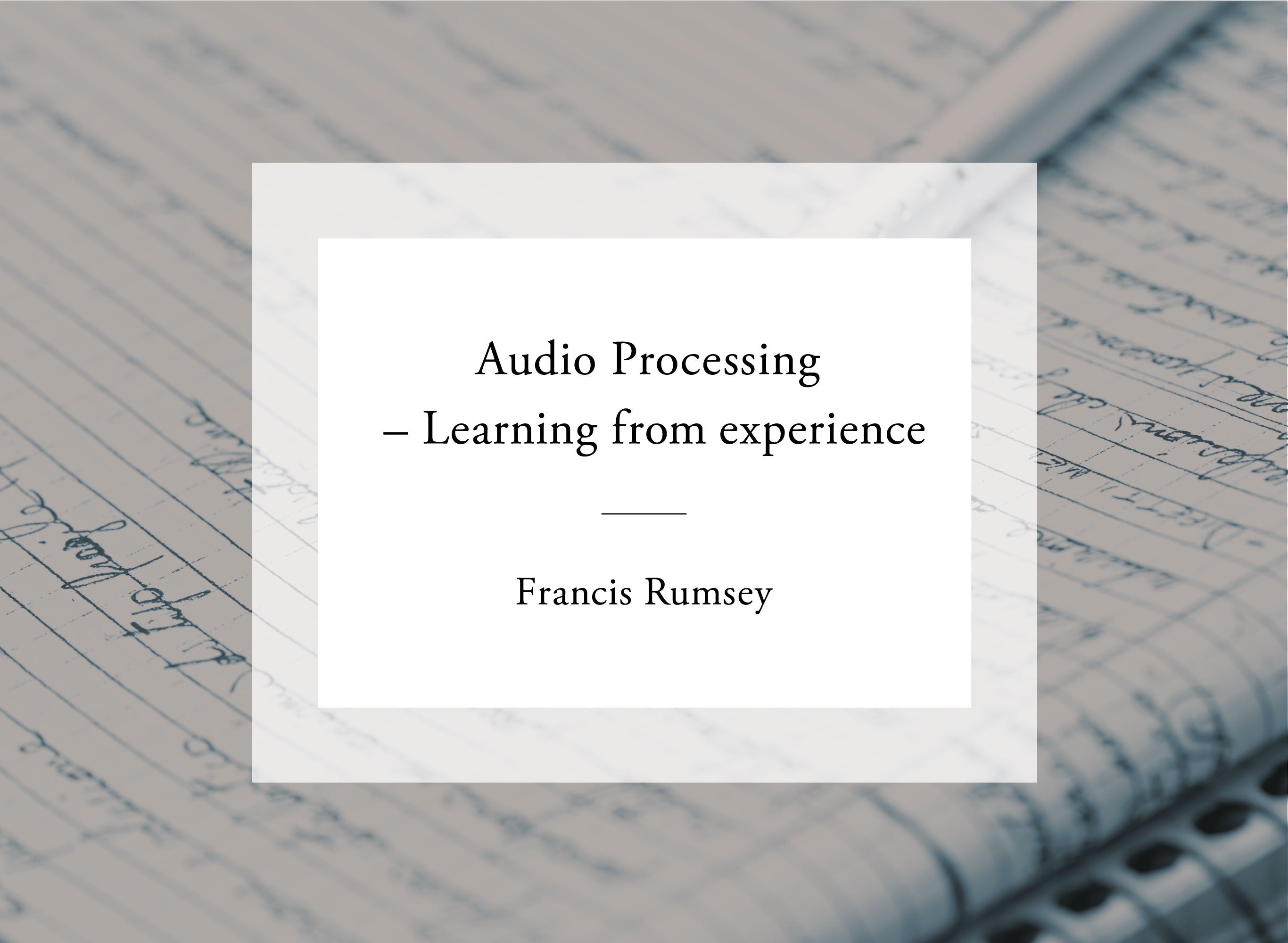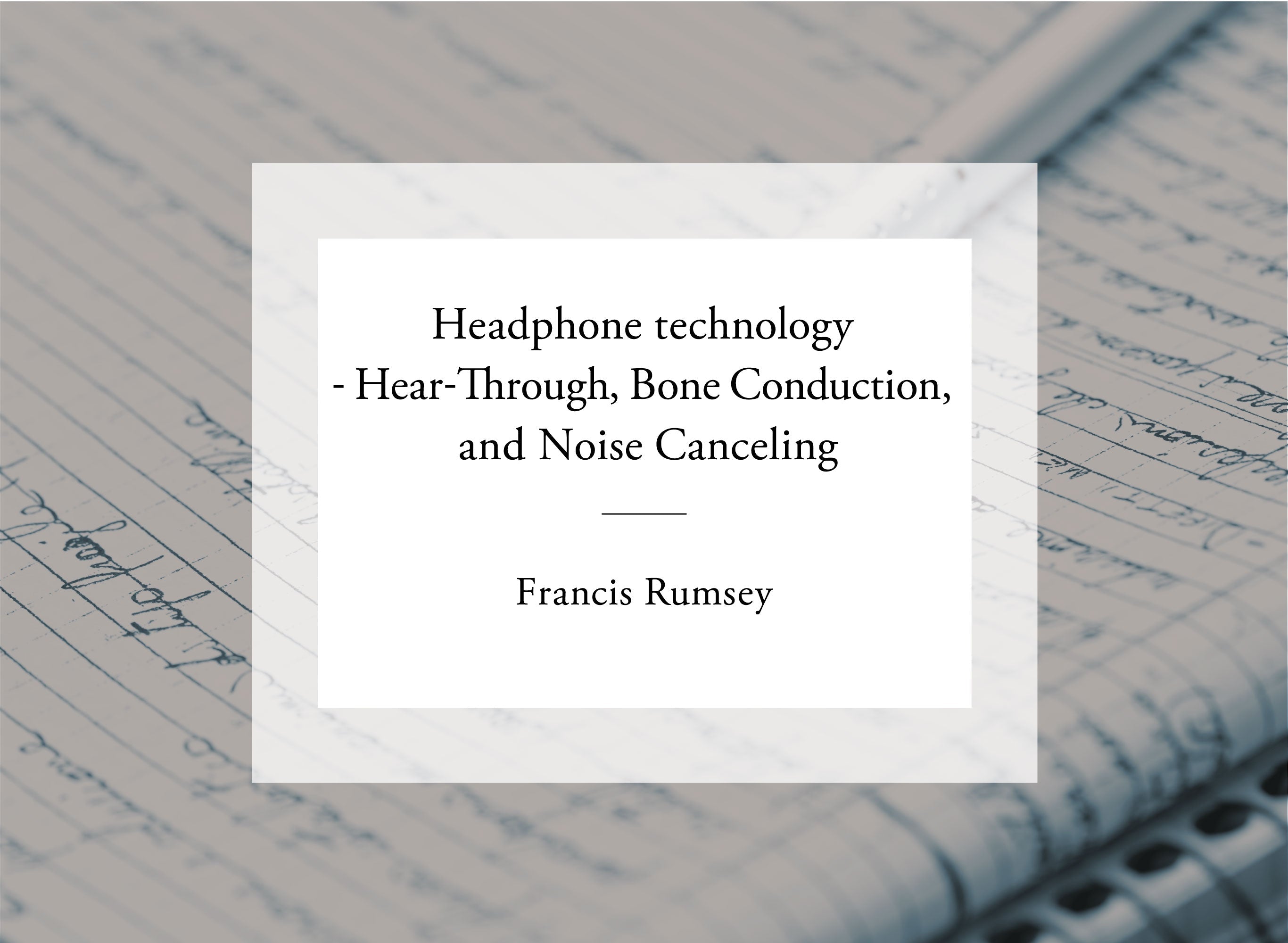音に関連した多様な分野で活躍される方々をお招きし、弊社チーフサイエンティストの濱﨑が、「音」についての様々なテーマについてお話を伺う企画です。 第1回目は、現在finalが共同研究を行なっている、九州大学大学院芸術工学研究院の河原一彦博士にお話を伺いました。お話しいただいたそのままを文章にしましたので、読みにくいところがあるかとは思いますが、これによって、文章から話し手の言葉そのものを感じ取っていただけることと思います。 4時間ほど伺ったお話を、主たる項目に分けてお伝えします。パート4は『研究テーマ』です。
九州大学大学院芸術工学研究院 河原一彦博士
・研究テーマ
・研究テーマ
濱﨑:ありがとうございます。ここまでが前置きで、ここからが本題です。今は、河原先生の所は、河原研究室とかいうふうに言われているのですか。
河原:一応言ってます。
濱﨑:私が大学にいた頃は、先生の名前は付かずに、第2講座とか言っていました。では、その河原研究室の研究について、ご紹介をお願いします。
河原:じゃ、研究テーマですね。大体、卒研募集のテーマと、今、大学院生とやっているテーマを書いてみました。僕自身が、信号処理の研究室の出身だったので、信号処理をベースにしている研究で、音響機器の応用と、音響機器の応用技術というようなことをキーワードにしています。スピーカー、卒研とか修士論文でやった信号処理とスピーカーというのは、まだまだ続いていてというか、まだ飽きなくて。僕があることで関わっていた分布モードスピーカっていうパネルスピーカーがあるんですけど、それの評価とか、使い道を探そうみたいなことを、これは、2000年くらいからずっとやっています。あとですね、2番目のやつは、これは大学院生とやっているんですけど、音場の評価として、聞き取りやすさという研究はいっぱいあるんです、明瞭度っていう研究があるんですけど、話す側にとって、話しやすいとか、会話しやすいっていうのは、ほとんど研究がないんです。めちゃくちゃ古い論文、昭和40年代くらいの論文とかしかなくて、あまり話しやすいとか、会話しやすいっていう切り口での音場の評価はなくて、そういうのに手を付けられないかなって、企業さんとの共同研究でもあるんですけど。話しやすい、明瞭度という指標から言うと、無響室みたいな空間で、静かで直接音しかなければ、明瞭度はすごく高いんですけど、無響室というのが、話しやすいとか、その中で会話しやすいかどうかというのは、それは、そうとも限らんだろうと。適度な反射音なり、適度な拡散性の残響なりが必要なんじゃないかなというので、確かに、それはそう思うけれども、それ、どうやったら調べられるのかっていう所から話し合っています、研究しています。大分、こうすれば調べられるんじゃないかっていうのが分かってきたところです。
濱﨑:話しやすいというのは、私が話す場合に、私自身が発声して話をしやすいということであり、私のほかに誰かがいて、その人の声も聞きつつ会話するということではなくてもいいわけですか?会話というのは、対象者がいないと成り立たないですよね。
河原:会話っていうのと組み合わせるのも、ちょっとやり始めてはいるんですけれども、どこかで1回切り離さないと。会話のしやすさをいきなり始めちゃったんですよ、実は。2人組になって、なぞなぞを解き合うとかいう、相手が言ってることを聞かないと、会話って成り立たないので。でも、そうすると問題が複雑になりすぎて、調べにくいので、会話しやすさを想定した話しやすさみたいなことですね。なので、自分の声がサポートされている感覚みたいなものです。よくステージ音響だと、ステージサポートみたいな表現がありますけれども。自分の演奏が自分で聞こえる強さみたいなもの、残響の適当な量みたいなものが、ステージ音響では研究されていますけど。同じように、普通の会話の際にも、話しやすさっていうのが、どうやら丁度良い初期反射音なり、丁度良い残響なりがありそうだぞというのを調べています。これは、僕自身が公共空間みたいな所に興味があって、レストランで会話をするにしても、話しやすさと、他の人の音の、他のお客さんの話し声の混じり具合というか、その分離だとか、そういうのが、空間の価値としてあるんじゃないかなと思っていて。とりあえず、他の人がしゃべっているのっていうのはちょっと置いといて、ある空間で話しやすいっていうのをまずちょっと切り出して調べてみようとしているところです。これ簡単そうで、割と難しいんですね。
濱﨑:話しやすいですか?って聞かれても、なかなか答えるのが難しいですよね。ただ、話すことを生業にしているアナウンサーとかいう人たちは、比較的小さな小空間のアナウンスブースみたいな所に入ってもらって、目の前に机が置いてあったり、マイクを目の前にして、しゃべってもらうということもある。そうすると、このブースは発声がしやすいとか、このブースはちょっと自分の音がこもって発声しにくいとかいうのは、アナウンサーからよく聞きますね。
河原:プロの話し手というのは、あるんですね、気持ち良く話せる所が。そういうのを知りたいんです。あわよくば、例えば小中学校の教室みたいな所の話しやすさみたいな、先生の話しやすさ、それと聞きやすさも含めてやらないと。これとスピーカーの利用技術とも関わりますけど、ある人と話していて、小学校とか中学校で、勉強が苦手な子がいるんだけれども、それ勉強が苦手じゃなくて、実は先生の声自体が聞き取れてないんじゃないかということをその方が、そういう可能性って、ありそうじゃない?っていうふうなことを言って。僕は、それをずっとモヤモヤ抱えているんですよね、確かにその可能性はあるなと思って。先生も楽に、気持ち良く授業をして欲しいし、それを聞き取る側も上手に上手く聞き取って欲しいなって思っていて。そういうために、あるきっかけで、会話のしやすさという所から始めたんだけど、会話のしやすさまで一気に行くのがやりすぎだったので、話しやすさというような所を音場での評価としてやってみようかなと思っています。これ、ありそうであまり研究されていない。
濱﨑:そうですね。先ほどお話があったステージにおける楽器の演奏のしやすさとか、あるいは、楽器のアンサンブルのしやすさとか、反射音というか、自分の音がどういうふうに反射されて帰ってくるとかは、やられていましたよね。でも確かに話しやすいというのは、明瞭度は一般にやられていますけど、意味合いはおっしゃる通り違いますよね。面白いと思います。
河原:やっていると、なんか関係あるパラメータが抽出できそうな気がして、あまり詳しくは、まだ僕も発表できる段階にないんですけど、こういうのに興味を持っています。あと、3番目ですね。これも10年くらい前からやっているリモートライブビューイングのための拍手・手拍子演奏ということで、これは、通信会社さんとの共同研究で始まったんですけど。これ、まず通信会社さんと高臨場感の伝送というようなことで、学内の教員チームとでやっていたんです。確かに、例えば、サラウンド伝送とかすると、ライブビューイングをしていても、例えば観客が自発的に拍手をしたりとか、そういうふうなことが観察されたりなんかして。マルチチャンネルにすると良いと、光伝送とかで、多チャンネルの音響・映像を配信できるようになると。これ、ある演目というか、当時、通信会社さんは、ある劇場と協業されていたんです。話を分かりやすくするために、ここだけ具体的に話を。劇場は、お客さんのマナーとして、声かけは禁止だったらしいんですよ。ただ、自分の席で拍手をするというのは、盛大にしていいよと。ライブビューイングに来られている方も、マナーで声かけはしないし、拍手をすると。それが実際にサラウンド再生とかするようなシアターだと、割と多くの人が拍手したりして、そういう行動が観察できたわけです。当時ですね、通信会社の研究員の方と打ち合わせをしていて、これは拍手しても、映画館とかでライブビューイングしていて、拍手しても届かないんですよねっていうのをなんとかしたいですよねって。僕自身もリモートライブビューイングを映画館とかで見ても、とても素敵なんだけど、僕の拍手も声援も届かないんだよなって思ってしまう所に非常に虚しさみたいなものを覚えて、それを解決してやろうっていうのを、やり方を考えたんです。当時は。この話長くなりますけど、いいですか?
濱﨑:いいですよ。どうぞ。
河原:ここに図面が見えていますか?
濱﨑:見えています。
河原:当時はですね、ライブの音声と映像が配信されると、こっちが映画館で、こっちが本会場みたいな所ですね、配信されますよと。ここで通信会社の方も、符号化の本当の専門家だったんですよ。ここで拍手を取り出して、どうやったら取り出せるかとか、拍手の成分を取り出して、拍手ってホワイトノイズっぽい帯域の広いノイズなので、それを符号化するのはめちゃくちゃ難しいんですね。どうやったら低遅延で伝送できますとか、できるようにしなきゃって、すごく難しいことをいっぱい考えて、どういう手法を使えば、ここで分離できますとかやっていたんですけど。実は、拍手そのものを送らないでもいいんじゃないかということに、2人で急に気がついたんですね。拍手しているという情報・状態を検出して、拍手しているよっていう情報を送って、拍手を合成すればいいと。手拍子しているよっていう情報を検出できれば、手拍子しているよっていう情報を送って、例えばリズムに合わせて同期するような手拍子を合成してやればいい。これで、学内で実験したんですけど、うちの大学には、多次元デザイン実験棟っていうホールがあって、そこで僕らの拍手・手拍子伝送をやったんです。これ、とても喜ばれましたというか、やりがいがあったんです。これは、研究はもうちょっとコロナより前に始めていたんですけど、これをなんとか社会実装したいというのが、僕の希望ですけどね。こういうライブビューイング、ネットワークオーディオの応用のための信号処理みたいなことをやっています。これ、どうですか?面白いかな。
濱﨑:最近無観客コンサートとかあって、そこに観客が存在しないというコンサートです。しかし、同じ空間で聴いている人がいて、初めて芸術が完成するわけですよね。聴いているという場を、どうやって作れるかが課題です。拍手も確かに重要ですよね。今年は、ウィーン・フィルのニューイヤーコンサートが、結局、無観客でやられました。事前に多分2,000人くらい応募者の中から選ばれた人たちが、インターネットで自分の自宅から普通に拍手したら、その音を全部足し算して、会場のスピーカーから出していましたよね。でも、おっしゃるように、あれはあくまでも個人の家だからできるんでしょうけど。ライブビューイング会場では、それができないので、この研究は非常に面白いんじゃないですかね。
河原:権利化したり、進んでいるんですけど、なかなかこう、社会実装というか、サービスに届いていないので、今年から何年かかけて、このサービスのパッケージ化みたいなものも視野に入れながら研究したいなと。今、色々な、さっきの図面の色々な要素部分の研究をしてきたので、その分早く色々な人に使ってもらえるようにしたいなと。またこういうフィードバックをすると、演奏者としても満足度がちゃんと上がるとか、観客も一体感みたいなものを感じられるというような、そういう調査も、きちんとしていかなきゃいけないなと思っています。
あと、今年の大学院生がやっているんですけど。彼は、僕の研究室に来て、録音の研究をしたいんですって言って。僕自身は、録音の研究をあまりやっていないけど、「先生は、色々コネがあるらしいじゃないですか」って言われて。そういう意味では、やったと。彼の切り口が尖っていて、録音された音楽のアナログ感は、どういう所に感じられるのかっていうトートロジーになっているんですけど。デジタル録音された音楽にアナログ感というのを感じられるのかなっていう難しい、ちゃんと考えると難しいんですけど。ひずみだったり、そういうことからアナログ録音された、もしくは、アナログでマスタリングされたような感覚を持つような録音というか、パッケージメディアの性質ってどういうことなのかなっていうのを調べようとしていて。今、だからパッケージメディアの音質を表す言葉とかをいっぱい集めたりしていますね。それが、どういう時に使われるのかっていうことも併せて調べ、研究を進めようとしています。これは、でも海外の人に話すと、それを割とホットな話題なんじゃないの?みたいなことも言われて、調子に乗って、ここに書いてしまいました。録音の品質の研究とかは、あまり研究するために素材を揃えるのが難しいので、元気のある人が学生さんと一緒にやらないと進まないかなと思っていますが。濱﨑さん、音楽のアナログ感みたいなのは、表現としては変ですかね。
濱﨑:私は、少し古色蒼然とした感じを受けます。昔は、こういう話はしましたよね。確かにデジタル録音が主流になったころ、特にロックやポップスでマスタリングする前に、1回アナログテープレコーダーを通して録音して再生したやつをもう1回、デジタル録音でやるとかっていうことは確かにやられて、まだ多分やっている所もありますよね。だからアナログテープレコーダーのヒステリシスカーブですよね。それによって、音が前に出てくるとかいう所があるんでしょうけど。
河原:例えば僕らの世代、50代60代のCDが出始めた頃のことを知っている人が、こういうキーワードを出すんじゃなくて、今の大学生が、こういうキーワードを持ち出したっていうのが、僕としてはびっくりして。
濱﨑:面白いですよね。確かに今、カセットテープがまた脚光を浴びて、カセットテープが売られ始めて、カセットテープに録音されたアルバムを売っていて、そこに若い人たちが、それを買いに求めるとか。それこそ、ビニールレコードも明らかに生産は増えている。それを買っているのは、昔アナログの時代でオーディオのマニアで、デジタルの時代を迎えたという人ではなくて、古い時代を知らない新しい若い人たち。そういう若い人が一体何をアナログ感と言っているのかという所に、ものすごく興味がありますよね。多分違うんだと思いますね、私たちが思っているアナログ感とは。
河原:僕は、この学生さんが修士論文を書き終わったら、彼が言いたかったアナログ感というのが物理的に説明できたら良いなと思っていて。
濱﨑:ぜひそうなると。ものすごく興味深いですね。
河原:僕自身も、今の段階では彼がどういう物理量、どういう聞こえをアナログ感と言おうとして評価しようとしているのかいまひとつ分からないんだけど、彼は、「間違いなくありますっ」て言ってるんです。なので、指導というか、サポートしながら、支援しながら進めたら面白いかなと思っています。録音、こういう研究を始めたのは、以前それこそAESの学会で、お友達というか知り合いになった所からの共同研究で、いわゆる好まれるミキシングのスタイルみたいなものが国別に違うかっていう共同研究をしたことがあったんです。それで、日本では九大が拠点というか、選んでもらって、パートナーとして選んでもらって、被験者を使って研究したんですけど。そういうのをして、録音の研究を実際やっているじゃないですかと、その学生が言ってきました。あれは、相手がいたからだけどねって言ったけど、中々彼も「こういうのをやりたいです」って。どうやってやるの?って言うと、彼なりにその場では、その時は考えてくれていたので、そこまで考えているんだったらやってみてっていうことで始めました。でも割と、もしかしたら面白いんじゃないかなと思います。あと、もう1つは聴能形成って言って。これは、音響設計学科でやっている授業なんですけど。耳のトレーニングというか。ザクッて言うと、耳のトレーニングなんですけど。これのカリキュラムを開発したりとか、音源を開発したりとか、そういうことをやっています。
>>続きを読む:Vol.1-5 『聴能形成とは』