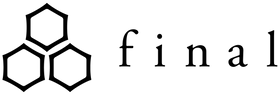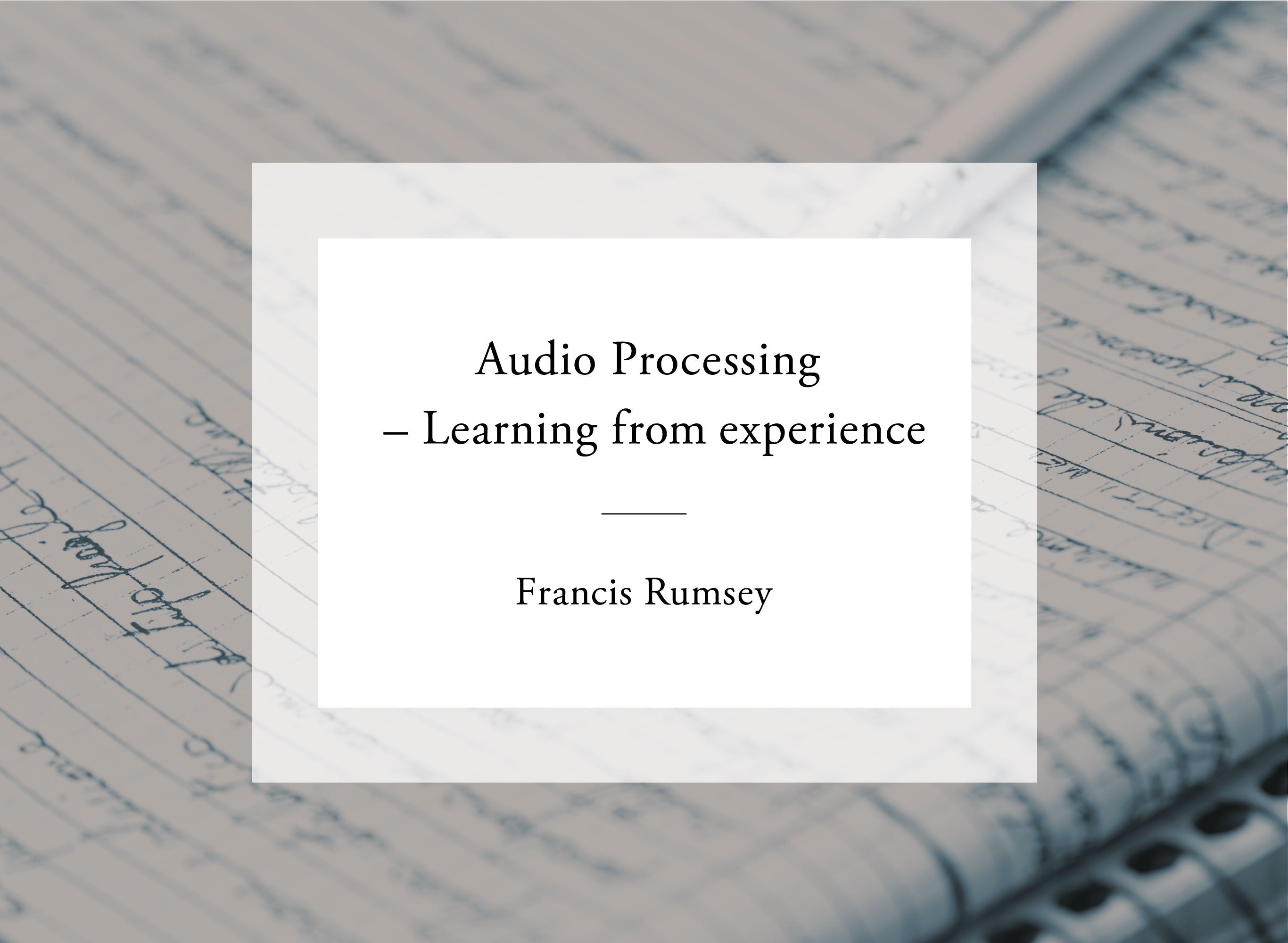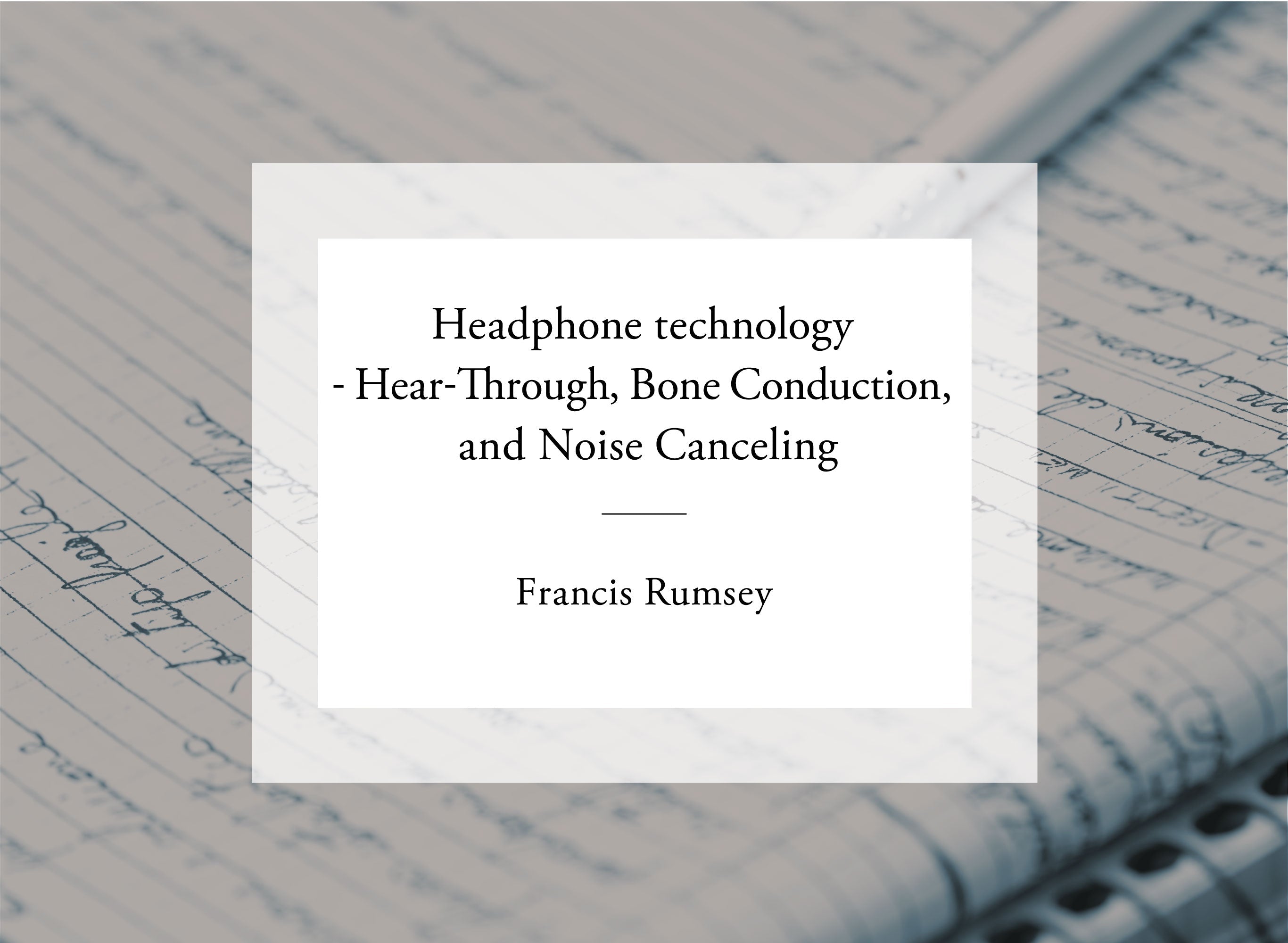音に関連した多様な分野で活躍される方々をお招きし、弊社チーフサイエンティストの濱﨑が、「音」についての様々なテーマについてお話を伺う企画です。 第1回目は、現在finalが共同研究を行なっている、九州大学大学院芸術工学研究院の河原一彦博士にお話を伺いました。お話しいただいたそのままを文章にしましたので、読みにくいところがあるかとは思いますが、これによって、文章から話し手の言葉そのものを感じ取っていただけることと思います。 4時間ほど伺ったお話を、主たる項目に分けてお伝えします。パート1は、『ご経歴』です。
九州大学大学院芸術工学研究院 河原一彦博士
・ご経歴
・ご経歴
濱﨑:今日は、河原先生に色々なお話を伺っていきます。最初に河原先生のご自身のご紹介をしていただけますか。よろしくお願いします。
河原:九州大学の河原と言います。よろしくお願いします。1964年のオリンピックの年、2021年の東京オリンピックの前の東京オリンピックの年に生まれました。福岡県内で生まれましたけど、ほぼ福岡市で、ずっと育っています。福岡県福岡市内の高校に行った後、87年に九州芸術工科大学の音響設計学科を卒業しました。大学院に進みまして、情報伝達専攻の修士課程を修了しました。研究テーマは音響信号処理。デジタル信号処理の研究室にいました。当時、日本に紹介されつつあった適応信号処理という、今だと普通にノイズキャンセリングのマイクとかもありますけれども、適応信号処理を使ったスピーカーのイコライゼーションの研究をしていました。その後、大学院を出た後、音響機器メーカに入社して、デジタル信号処理の業務用のツールだとか、デジタルミキサーの開発に関係していました。平成3年、1991年に、九州芸術工科大学の助手として戻ってきて、現在は、准教授ということで務めさせていただいています。社会活動というか、日本音響学会っていう所で、音響教育委員会の委員長を仰せつかっています。あと、オーディオエンジニアリングソサエティ、つまりAESという所のエデュケーション・コミッティという教育の委員会がありまして、ここでアジアの副委員長、バイス・チェアを務めています。経歴としては、こういうことです。このインタビューの準備をしながら、自分でもなんで音を志すというか、音に興味を持ったんだろうなって思って。
濱﨑:河原先生、お話の途中で止めてしまいますが、音に興味を持つようになったきっかけを伺う前に、少し質問させてください。大学院の修士研究でデジタル信号処理の適応信号処理をやられて、89年に、音響機器メーカに入られて、デジタル信号処理やデジタルミキシングシステムの開発などをやられていたんですけれども、この時代って、信号処理としては大分こなれて、実用化が進み始めた時期でしたか。
河原:時代的には、メディアとしてコンパクトディスクが普及し始めたっていう感じですかね。レコードからCDに乗り換わってきて。機器としては、この頃、調整・業務用の機器なんかでは、1サンプリング周期にコマンドが DSP(ディジタル信号処理プロセッサ)で100ステップも計算できなかったんじゃないですかね。DSPのチップのプログラミングをする時に、どのコマンドとどのコマンドは同時に実行できるからというようなことで最適化をしていました。僕自身は、あとは、DSPによっては、マイクロプログラミングっていって、中で別のプログラミングのやり方、別の実装のやり方をしていたんですね。デジタルで音が扱えるようになって、例えばEQだとか、そういうのをリアルタイムに専用のハードウェアを使えばできるようになったけど、何に使うんだろうみたいな、そのほか、そんな信頼性のないものを使っていいのか?みたいな話もあったようですね。後から振り返ってみると、デジタル信号処理のものを使って、途中で止まったらどうするんだ?みたいなことは、すごく言われていました。アナログだと、不具合があっても、じわっと変化するから安心だという時代だったんですね。デジタルだと、実際に昔話で聞いたのは、本番直前にフリーズしてしまうような時もあったらしくて。そういう機器を本番に使うのは怖くてできないから、アナログの機材しか使わないっていうようなSR(Sound Reinforcement、音楽コンサートなどで大勢の観客に高音質な音を聞かせる業務)の分野では一発勝負なので、そういう所にデジタルの機器がエフェクターとして入れていいのかどうかみたいな、そのような時代だったと思います。
濱﨑:1989年は、私は結構個人的には、よく覚えているんですけれども。ソニーの24トラックのDASHフォーマットのデジタルテープレコーダーが使えるようになって、それを日本からミュンヘンに運んで、ミュンヘンの州立歌劇場でワーグナーのニーベルングの指環という、全部やると12時間くらいかかるオペラを、アナログを全然使わずに、全部デジタルで録ったんですね。テープが200本くらい。テープに録音して、日本に持って帰ってきたんですけど、テープにデジタルで録音するという意味では、信頼性がいけるかなとかいう時代で。ところが、録った音をじゃ、今みたいにパソコンで編集できるかというと、そういう時代ではなくて。やっと当時、英国のAMSから今のDigital Audio Workstationの先駆けとでもいうべきデジタルオーディオ編集装置、専用のOSを持った機器が出て、2chステレオのデジタルオーディオ信号であれば、多少のイコライジングとか、ピッチを変えずに時間軸を伸ばすとか、縮めるとかができた。これを駆使して、12時間のオペラのポストプロダクションを4か月間休みなしで何とか終わらせることができた。そんな時代ですよね。その頃。
河原:だったと思います。多分、濱﨑さんがそういうふうにフルデジタルで録音するというような、おそらくチャレンジというか、大冒険だったと思うんですけど、そういうのをされて、全部デジタルだと大丈夫なんじゃないかっていうのが、そういう挑戦者がいたという時代じゃないですかね、80年代終わりというのは。それ以前は、所々デジタルの機材が混じっていて、それの両端にAD-DAが付くので、余計不安定になっていて。僕らが会社で関わったデジタルミキサーのシステムを当時のリーダーが、全部デジタルだったら問題ない、動かなきゃいけない、動くはずだというような信念の下で。もちろん信頼性のための色々な工夫はしましたけれども。おそらく、業界で、ライブで使うためのフルデジタルのミキシングシステム、SRのためのシステムというのは、世界初だったんじゃないかなと。
濱﨑:そうですよね。まだまだアナログ。信頼性と、それから、音が良いとか悪いとか、この時代は議論していました。デジタルってデジタル臭いねとか、アナログに比べたらみたいなふうに。デジタルとアナログって、どうなんですか?みたいなことを、何か講演してくださいって言われるとその話をしたりなど、若干私も先を走りすぎてはいました。おそらく、デジタルミキシングシステムも、そういったライブパフォーマンスで、全部デジタルシステムでやるというのは、極めて世界的にも先駆的でした。でも誰かがそれをやらないと、いつまでたっても分からない。アナログだとかデジタルだとかいうことで議論ばかりで前に進まなかった時代ですから、丁度そういう意味では1989年90年91年っていうのは、プロの方では大分デジタル化が進み、おっしゃったように、CDも普及し始めて、いよいよ、じゃあ信号処理を本格的にどう使うかという所ですけど、先ほどあったように、デジタル信号プロセッサーのDSPの計算能力が今に比べると、まったく厳しかった時代ですよね。
河原:そうですね。どれくらい違うのかな。今のスマホに入っているようなものの何百分の1くらいの性能しかなかったと思いますね。大変。ただ、その制約の中で何ができるのかみたいなことは、僕らテストしながら。本当に会社時代は、DSPのマニュアルを隅から隅まで読んで、このコマンドとこのコマンドは、一緒に使えるとか、実は、複数のコマンドを一度に動かすための制約みたいなものがあったりして、そういうのを隅から隅まで読みましたね。でも、よく考えられているなっていうふうにも思いましたね、確かに。
濱﨑:河原先生が大学に入られた頃は、デジタル信号処理っていうのは、カリキュラムには入っている時代だったんですか?
河原:そうなんです。僕が九州芸術工科大学の16期生なんですけど、初めて学部にデジタル信号処理という授業が入った学年なんですね。それを4年生の前期に取りました。今は、2年生の後期にデジタル信号処理の授業があるんですよ。それくらいデジタルが当たり前。信号処理の授業が、当時僕の2年生の時に、フーリエ変換とか、そういうのを習っていましたけれども。4年生の前期に、興味があれば取ってもいいよみたいな位置付けですね。4年の前期なので、デジタル信号処理の先生が、「君らから初めて学部で教えるから」って。それまでは、大学院に進学しないとデジタル信号処理っていう授業は、なかったんですよね。なので、デジタル信号処理っていうのが、受け入れられ始めたというか、大学としても、教えないわけにはいかないだろうっていうふうな改定があった時期かなというふうに思っています。
濱﨑:スピーカーの等化の研究を修士論文でやられたんですよね。これスピーカー等化ということを選ばれた何か目的というのはあったんですか?信号処理の応用として。
河原:そうですね。学部の時の指導教官、学部の指導教官の先生が、適応信号処理のスピーカー等化のことをアダプティブスピーカーの研究というふうに卒研募集の一覧の中に書いてあって。何ですか?って先輩に聞いたら、アダプトするんだよって言われて。よく分からないけど、スピーカーと信号処理が一緒になった研究なので、スピーカーのことも興味があったし、それをデジタル信号処理で何か良いことをするのかなと。3年生の終わりに応募する時は、イコライザーを自動設計するということまでは理解していなかったですけど、信号処理とスピーカーが一緒になった研究なんだっていう所までは理解できて、申し込んで、それでやりました。適応信号処理、実際に、修論はすごく特定の分野での条件が色々付いたような内容だったんですけど、スピーカーと信号処理と両方のことを考えながらやる。特にイコライザー。スピーカーって、どうしても振動板があることの物理的な制約で、直流が再生できないとか、分割して振動しちゃうとか、あと、音響中心が周波数によって変わるとか、そういうふうな問題とかがあるので、そういう研究を進めながら、なんとなく理解したという感じかな。だから、当時の僕の理解は、そこまで。結局まだこの時、修士研究ではシミュレーションしかできなかったんですよね。会社に入ったら、それをハードウェアを設計して、DSPのプログラムにも書けば、リアルタイムで動くかもしれないみたいな。それだったら、一生懸命仕事をしようって思いましたね。ハードウェアの技術は、そこまで来ているんだなって思って。シミュレーションだけやっていて満足していたらダメだなっていうか、そういう世界があるんだって。ハードウェアを作って、自分でDSPのプログラムを書くと、制約はあってもリアルタイムで動くっていうのが、すごく興奮しましたね。大学にある当時のスーパーミニコンピュータとかでは、1秒間の出来事を一晩かかって計算していたくらいなのに、1秒間の出来事を1秒間で計算できちゃうっていう、リアルタイムにできちゃうっていうのは、その時の当時のDSPでも、感動しましたね。
濱﨑:リアルタイムの畳み込みまでは、まだできなかった時代ですかね。
河原:畳み込み専用のためのフィルター、デバイスが開始されていましたね。当時、モトローラ。今はDSPを作ってないし、MPも作ってないですけど。モトローラって、当時おそらくWindowsから見たAppleみたいな感じで、インテルから見たモトローラって、すごく洗練された印象だったんですよ。インテルとか、Z80ですね。Z80やH8のマイコンとかから見ると、モトローラってすごく洗練されていて。モトローラのDSPですね、スティーブ・ジョブズのNeXT Computerが搭載したDSPは。DSP56000シリーズだったかな。それに実は、そのシリーズに適応処理専用のデジタルフィルターの姉妹部品があって、モトローラのDSPとモトローラの適応信号処理用のフィルターを組み合わせて、僕の大学院時代の野望みたいなものを会社の研究開発活動の一部としてやったりさせてもらっていました。それは、もしかしたら売り物にできるかもしれないから、ちゃんとやれっていうのもあって。ただ、DSPと特殊なデジタルフィルターを密集させて配置すると、すごく熱くなっちゃって。蓋を閉められないようになっちゃって。熱設計というのはこういうことかっていうのと。あと、思い出したんですけど。当時、1サンプリング周期がns単位で考えていて。1nsに電子は30センチしか、確か30何センチしか進めないんですね。そうすると、ある部品を突いて、例えばハイからローに論理値を変えても、その部品の反応速度があったりすると、基盤の端っこから端っこまでの部品とやり取りさせようとすると、返事が間に合わないとか。そういう、実は光の速度って速いと思っていたら、そうでもないんだなとか。そういう電子のスピードの限界みたいなのを実感しましたね。本当に伝わってないから、どうやっても当時の僕のプログラミングの技術として、この部品がこういう命令をして、反対側の相手の部品が返事しないんですよって言ったら、それ間に合ってないんじゃないかって、ある先輩に言われて。何のことですか?って。だからずっと回路トレーサーみたいなの使い方を教えてくださって。実は、返事はしているけど、自分が欲しい時間・タイミングでもらえないから、このタイミングでは、ちゃんと1ステップ待たないといけないよねとかいうような経験もさせてもらいましたね。とても電気の速さというか光の速さの限界みたいなものを感じました。そういう色々な経験をさせてもらいました。音響機器メーカでは色々な経験をしましたけど、デジタル、そういう仕事だけじゃなくて。会社入った時に、芸工大から来ましたって言うと、機構屋さんかな、機構担当の他部署の人が、「君、電気分からへんねんな。まあ、頑張れや」って言われて。僕自身は、電気得意ではあったんですけど、電気分からへんねんなって、きついなと思ったんですけど。おそらく、それは電気分からないけど、違うことを知っている人たちっていう評価が既にあったんじゃないかなと思っていて。なので、僕は先輩たちの活躍のおかげで、会社でのびのびと仕事をさせてもらえたのかなというふうに思います。あとは、会社で言われたのは、割と職人みたいな技術者がたくさんいるので、その人に信頼されるようになりなさいっていうのは言われていて。今でも、すごく印象というか、信頼されるというようなことで。本当に雑談ですけど、僕、開発の途中に、開発の初期段階に、ある特注のユニットをやりなさいと言われて、1Uのラックマウントの1ユニットサイズの外付けのパーツを作っていて。回路は、大体先輩がたたき台を作ってくれていて、それを参考にしながら変更してやったんですけど。回路は、なんとかできた。特注なので、パネルに電源ボタンとLEDとパイロットランプと、後ろにキャノンコネクタを付ける穴を開けないといけない。穴を開けるのに、試作屋さんというか、試作専門の機構の担当の方がいらっしゃって、その人は怖いというか、厳しい人だって聞いていたので、かなりビビりながら自分で書いた図面とパネルを持って行って、「試作して欲しいんですけど」って言ったら、僕の図面を見て、チラって横目で見て、「そんな図面で作られへんで」って。「穴、3つ開けてもらえたらいいんですけど」って言ったら、「穴の数ちゃうねん」っていうふうに言われて、プイって。それで、ご自身の作業に戻られて。部屋に、自分の机に戻って、「怒られちゃいました」って言ったら、僕は当時知らなかったんですけど、機構部品は機構部品で、こういうふうにパネルのこっち側から測るかとか、こっち側から測るかとか、そういう基準をちゃんと揃えておかないといけなくて。僕は、右から測ったり、左から測ったり、自由すぎたと、次の日、先輩に教えてもらいながら、図面を書き換えて持って行くと、「すみません。昨日の図面、書き換えてきたんですけど。これで作ってもらえますか?」って言ったら、「それ置いといて」って言われて、作ってくれたんですけど。その日のお昼休みか何かに、その人が食堂に行く時に後ろから追いかけてきて、「君、面白いことをしているって聞いてるで。また声かけてや」って言って去っていかれたんです。びっくりしたなと思って。それは、多分僕の勝手な好意的な解釈ですけど。図面を1日で書き換えてこれる奴って思われたんだろうなと思って。芸工大生の音響生は、製図だったり、そういうのが苦手なんですけど。それさえ乗り切れば、本当の専門家が力を貸してくれるんだなっていう体験は、会社員時代にさせてもらいましたね。すごく。それから後、開発では芸工大というか、音響設計学科だったからかもしれないですけど、ジッパーノイズ。当時、まだジッパーノイズ、デジタルミキサーのフェーダーのゲインを変えて、それをサンプリング周期ごとにゲインを変化させていくと、バリバリバリって、ジッパーのノイズみたいなふうに言われていたんですけど。それを上手くスムージングしないといけないと。どれくらいの遅れまで許容できるかみたいなのを、当時、デジタル回路というか、デジタル回路が専門の、僕から見たら、スーパーエンジニアの人が、色々チューニングしているわけですよ。たまたま開発の部屋で、2人でちょっとだけ残業して。僕は、僕のさっきの実験基板を、実験というか、開発テーマの基板をいじっていたというわけですけど。その方が、「なあ、ジッパーノイズあんねん」って、「フェーダーとゲインと、どれくらいまで遅らせるんやったら人には分からへんねんやろうな」。ちょっと、どんな関西弁だったか覚えていないんですけど、どれくらいだったら分からないだろうねって言われて。僕、すぐ「20msまで大丈夫だと思いますよ」って言ったんですよ。その人は、僕がすぐ答えたのが不思議というか、「お前、バカにしとるんか」って言われたんですけど、「そうですかね」って言って。僕は、聴覚のハース効果とか一瞬考えて、20msくらいだったら、分離できないだろうなと思ったから、分からないだろうなと思ったんですね。次の週、同じようなシチュエーションで、2人で残業していて、「この前の話さ」って言って。僕は全然覚えていなかったんですけど。「この前の話さ、やっぱり20msくらいが丁度良いな」って言われて。僕としたら、「それがどうしましたか?」って言ったら。「芸工大の人は、みんなそんなこと知ってるの?」って言われて。「知ってるんじゃないですか」って言って。「そういうの知ってるんだね」って言われたのが、僕は逆に不思議だったんですけど。芸工生、芸工大の芸術工学部の音響設計学科っていう所が、きちんと音に関する教育をしていたおかげなのかなと、特徴が出ているのかなというふうに思いました。今思うと、あのやり取りというのは、芸工音響設計学科とか音響設計コースの人たちの強みと弱みの表裏一体みたいな所かもしれないですけど。強みでもあるわけですね、そういう信号処理と聴覚が、きちんとつながっているという所が。そういう体験を、僕、2年間は実はいなかったんですけど、その中で、すごくいっぱい色々な勉強をさせてもらったのが、会社員時代ですね。
濱﨑:2年間というのは、音響機器メーカでの会社員の生活が2年間ということですね。
河原:そうですね。
濱﨑:2年間で、その後に助手として大学に戻られるんですけれども。これは、大学の方から戻ってきてくださいみたいな、何かきっかけがあったんですか?
河原:そうですね、一応、僕も大学、芸術工科大学っていうのに戻ることに対しては、非常に興味があって。おそらく、他の大学から声がかかったとしても、音響機器メーカは十分良い環境だったので、行くことはなかっただろうと思いますね。九州芸術工科大学っていうユニークな環境に戻りたいっていうのと、教育研究に関わりたいっていう気持ちはありました。それで、大学の人事の都合とも合ったようで。
濱﨑:タイミング良く。
河原:そうですね。
>>続きを読む:Vol.1-2 『音に興味を持ったきっかけ』