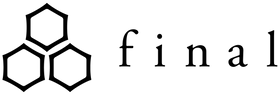音響やオーディオ技術に関する専門用語、音響やオーディオの研究開発において必須な物理、数学等の学問で用いられる用語、音響やオーディオ技術のトレンドとして注目している技術に関する用語などを紹介します。
キーワード:自由音場、無響室、吸音くさび、音響インピーダンスマッチング
近年、半導体技術の進歩に伴い、データ保存用メディア、信号処理やワイヤレス伝送などの技術が飛躍的に進歩してきました。これによって、個人向けのエンターテインメント製品もより多く開発できるようになりました。こういったエンターテインメント製品の中で、映像や音響の製品、ならびにデータ保存用メディアを利用した製品が特に進化してきたと感じています。例えば個人向けの映像製品には、タブレット、VR用ゴーグル、小型プロジェクターなどがあります。また音響製品には、ワイヤレスヘットホンおよびイヤホン、ポータブルスピーカー、ワイヤレス・デスクトップ・スピーカーなどがあります。そして、データ保存用メディアには、SSD、Micro SDカードなどの製品があります。
現在、いろいろなメーカーが音響製品の開発に参入し、エントリーモデルからハイエンドモデルまでたくさんの製品が開発されています。そして、音響製品の機能と性能をアピールするため、評価や測定の手法も重視されつつあります。
音響製品の音響特性を測定するうえで、一番信頼できる場所は「無響室」だと思います。無響室は、反射音がない部屋です。理想的な無響室では、音響製品から音を出すと、壁に当たる音が全部吸収され、部屋のどこにいても、音響製品から発せられる直接音しか聞こえません。つまり理想的な無響室は、音響製品から放出される音を、反射音に影響されることなく、正確に測定できる環境なのです。ただし実際の無響室では、吸音特性は内装の性能に影響されます。例えば、音響製品の測定を目的とする無響室は、可聴帯域の音を主として吸収するように設計されています。一方、電波を発する通信機器のための電波無響室は、電磁波を吸収できるように内装が設計されています。
finalでは、より良い音響製品を開発するために、無響室での測定や試聴評価を頻繫に行っています。以前、final LAB Twitterで無響室に関する投稿をしましたが、今回は、無響室発展の歴史に着目したいと思います。無響室の歴史を振り返ると、無響室を使用する際に注意すべき重要なポイントを知ることができます。そして、無響室のことをもっと知っていただければ、音響製品の仕様や性能などの音響測定データを見ていただくときに、より身近に感じていただけると思います。音響製品を開発する私たちと、音響製品をお使いいただく皆様の双方で、無響室での測定がいかに重要かを理解していけば、音響製品に使用される技術のさらなる発展に繋がっていくものと信じています。図1. 無響室でのfinalによる音響測定の様子
筆者が参照した文献の中で、無響室に関する最初の記述があるのは、1951年の文献です[1]。この文献が紹介しているのは、1928年の英国メトロポリタン・ヴィッカース電気会社(Metropolitan Vickers Electrical Company)の実験室でした。当時はまだ「無響室」という名称ではなく、「自由音場(Free field)に似せる実験室」と呼ばれていました。しかも、音響機器開発のためではなく、主に電気モーターなど機械騒音を測定する実験室として使用されていました。残念ながらこの最初の音響実験室の写真はありません。図2は、その音響実験室を1933年に増築した第二実験室です。
図2. メトロポリタン・ヴィッカース電気会社にある反射がない実験室[1 pp. 158 Fig. 11]
1936年、E. H. Bedellはベル研究所で自由音場を作り出すことを試みました[2]。複数の布を多層に重ねた平坦な吸音体サンプルを試作し、そのサンプルを垂直入射法(音響管法)で測定した結果、高い吸音率があることを確認しました。ただ、この吸音体を使用して完成した実験室の吸音率を実際に測定したところ、予想した吸音率より低いことが分かりました。当時は吸音体に対する音波の斜め入射を考慮していなかったため、こういった結果になったのだろうと思われます。
1940年、ドイツの学者Erwin Meyerは、初めて音響インピーダンスをマッチングする概念を発表しました[3]。つまり、吸音材と入射音の音響インピーダンスがうまくマッチングしないと反射が起こり、吸音効果が低下するということを発表したのです。この理論に基づき、彼はピラミッド状の吸音体を提案しました。さらに、吸音体の寸法と吸音率との関係も詳細に検討し(Parametric study)、吸音体の形状を最適化しました。こうして、ロックウールを充填した吸音体32000個を図3のように部屋の中に配置しました。この実験室において、被測定音源から3メートルの範囲の幾つかの測定点において音響測定した結果、各周波数帯域の音圧減衰予測値に対して測定結果が2 dB以内の偏差に収まっていることがわかり、十分な性能を有する音響実験室が完成したわけです。
図3. Erwin Meyerが設計した音響実験室[3 pp. 361 Fig. 12]
1943年、アメリカの学者Leo L. Beranekは、第二次世界大戦中、政府からの依頼を受け、ハーバード大学で音響実験室を設計しました*[4]。彼は自由音場ということばを言い換え、「echo- free (Anechoic)」つまり「無響」ということばを初めて用いました。彼も音響インピーダンスマッチングの理論に基づき、吸音体の形状を実験で検討しました。また、Meyerが提案したピラミッド状の吸音体は製造と設置のコストが高いことを指摘し、くさび状のほうが効率的だと主張しました。さらに吸音効果を高めるため、吸音体の背後に空気層を設けることも提案しました。Beranekは逆二乗則の測定結果と、Meyerも使った減衰予測値の偏差値の測定結果をもとに、完成した無響室が十分な性能を有することを示しました。残念ながら、第二次世界大戦後、アメリカ政府は戦時に建造したものを取り壊すという目的で、ハーバード大学に二つの提案をしました。一つは、アメリカ政府が費用を負担し、すぐに取り壊すというものです。もう一つは、ハーバード大学が1ドルで無響室を買い取り、今後の運営費用は大学側が負担するというものです。当時のハーバード大学には無響室を利用する研究がなかったので、この無響室が撤去されてしまいました。[5]
*著作権により無響室の写真を掲載できませんが、興味がある方は、Googleでの検索でご覧いただけます([リンク])。
Beranekの研究成果に影響され、くさび状吸音体はほぼ無響室の標準仕様になっていきました。1947年にベル研究所もくさび状吸音体を使って、確認できる範囲でいえば、現存するなかで最古の無響室を建設しました**。
**著作権により無響室の写真を掲載できませんが、興味がある方は、Googleでの検索でご覧いただけます([リンク])。
くさびやピラミッド状の吸音体は音響インピーダンスマッチングの理論を利用したよい設計ではありますが、吸音体に関する研究は終ってはいません。最近の研究動向を以下ご紹介します。
一つめは、吸音体の形状の最適化です。くさび状吸音体の設計数式([リンク])では、下限周波数は吸音体の長さ(長さとはくさびの根本から先端までの距離を意味しますが、本文では、以降、長さを厚みと書き換えます。)にしか関係していませんが、実際はそれだけではありません。吸音体に用いる均質材の吸音特性と、吸音体の形状によって、音響インピーダンスが変化します。そして音響インピーダンスが入射音と吸音体でマッチングしない場合、吸音体の吸音性能が落ち、設計式から算出された下限周波数に、実際に吸音できる下限周波数が届きません。無響室の設計検討が始まった当時、材料技術が今ほど進歩していなかったため、使える吸音材は限られていました(均質材のロックウール、グラスファイバー、布など)。また、吸音材の音響特性も十分に把握できていなかったため、音響インピーダンスをマッチングさせるには、実験検証で適切な吸音体の形状を探すしかありませんでした。均質材で吸音体を作るのが最もコストが低いため、今でも、均質材による吸音体を用いるのが無響室の主流です。ただし当時と異なり、材料技術の進歩により、使える均質材は多様になり、例えば、よく使われるグラスウールでも密度を選べるようになりました。現在は32kg/m3、64 kg/m3、96 kg/m3などから選べます。あるいは安全性が高いポリエステル材も使えます。また、吸音材の研究も進んで、吸音材の音響特性をパラメーター化することもできるようになりました。加えて計算機や、シミュレーション技術も進化し、短時間にたくさんの吸音材と形状の組み合わせを検討することができるようになったため、材料や形状を最適化した吸音体を設計することが可能になりました。
二つめは、吸音体の薄型化です。Meyerが完成した無響室では、ピラミッド状吸音体が室内全容積のおよそ50%も占めていました[4]。この吸音体が膨大な容積を占める問題を解決するために、吸音体の厚みを薄くする研究がたくさん行われました。1963年、小林理学研究所の子安勝は吸音体の先端は弱くて、人や機材が接触したら破損する可能性があることを示しました。さらに、くさび状吸音体を先端からテーパの全長の30%までカットしても、吸音特性はほとんど変わらないことを実験で明らかにしました[6]。こうして無響室内の有効範囲をさらに広げることができました。現在、国内におけるくさび状吸音体を使っている無響室の吸音体がほぼ台形になっているのは、こういった研究があるからです。ちなみに、海外にはまだ先端がカットされていない無響室がたくさんあります。図4. 先端をカットし台形になったくさび状吸音体
さらに近年では、吸音のメカニズムに関する研究と材料技術のさらなる進化によって、多様な吸音構造や材料を組み合わせた吸音体も製造できるようになりました。この複層材料を利用して音響インピーダンスマッチングを検討することによって、くさび状吸音体より薄く、吸音性能も劣らないフラットな吸音体の開発に成功した研究が報告されています[7-8]。その一例が、図5に示した、ドイツのFAIST社による厚み350mm、下限周波数50Hzの吸音体です。図5. ドイツのFAIST社が開発した吸音体の概念図[8]
くさび状吸音体で反射音をなくした無響室の歴史は長く、これまでの研究の積み重ねで、その理論と設計手法も明確になりつつあります。ただし、くさび状吸音体の難点といえばその厚みです。下限周波数を低くするためには、かなり厚いくさび状吸音体を用いなければならず、その結果、無響室を作るためには、広い土地と空間が必要となります。しかしながら、複層材料による薄い吸音体が開発された結果、無響室建造に関する先決条件(床面積、室内空間容積)が緩和され、よりコンパクトな無響室の実現が可能になりました。さらに工場や会社などの室内に置くことも可能な、組み立て式で持ち運び可能な無響室や無響箱も開発されています。もちろん、こういった組み立て式無響室が吸音できる周波数帯域幅は、まだ従来の無響室より狭いです。しかしながら、こういった技術の研究開発がさらに進めば、今後、より小さな室内空間(例えば6畳の部屋)内にも、無響室を作ることができるようになるのではないかと期待しています。
参考文献
[1] A. Fleming, B. G. Churcher and L. J. Davies, “The research laboratories of Associated Electrical Industries Ltd.”, Proc. Roy. Soc. A, vol. 210, issue. 1101, pp. 145-172, 1951.
[2] E. H. Bedell, “Some Data on a Room Designed for Free Field Measurements”, J. Acoust. Soc. Am., vol. 8, pp. 118-125, 1936.
[3] E. Meyer, G. Buchmann and A. Schoch, “Ein neue Schallschluckanordnung hoher Wirksamkeit und der Bau eines schallgedämpften Raumes”, Akust. Z., vol. 5, pp. 352-364,1940.
[4] L. L. Beranek and H. P. Sleeper, “The design and construction of anechoic sound chambers”,J. Acoust. Soc. Am., vol. 18, no. 1, pp. 140-150, 1946.
[5] No Writer Attributed. (1971 March 30). Eerie Echoless Room Torn Down With Lab. The Harvard Crimson.
[6] 子安勝, “防音室・無響室・遮音室ー要求される性能と実現の方法についてー”, AUDIOLOGY, vol. 6, no. 4, pp. 269-277, 1963.
[7] J. F. Xu, J. M. Buchholz and F. R. Fricke, “Flat-walled multilayered anechoic linings: Optimization and application”, J. Acoust. Soc. Am., vol. 118, no. 5, pp. 3104-3109, 2005.
[8] Helmut V. Fuuchs, Xueqin Zha and Gerhard Babuke, “Broadband compact absorbers for anechoic linings”, CFA/DAGA, Strasbourg, 2004.
謝辞および著作権に関する説明
図2は参考文献[1]から引用し、Proceedings of the Royal Society Aの著作権ポリシーを遵守し写真掲載を行っています。https://royalsociety.org/journals/permissions/
図3は参考文献[3]から引用し、当文献はオープンアクセスになっており、こちらの[リンク]から閲覧できます。
Seki
現在、いろいろなメーカーが音響製品の開発に参入し、エントリーモデルからハイエンドモデルまでたくさんの製品が開発されています。そして、音響製品の機能と性能をアピールするため、評価や測定の手法も重視されつつあります。
音響製品の音響特性を測定するうえで、一番信頼できる場所は「無響室」だと思います。無響室は、反射音がない部屋です。理想的な無響室では、音響製品から音を出すと、壁に当たる音が全部吸収され、部屋のどこにいても、音響製品から発せられる直接音しか聞こえません。つまり理想的な無響室は、音響製品から放出される音を、反射音に影響されることなく、正確に測定できる環境なのです。ただし実際の無響室では、吸音特性は内装の性能に影響されます。例えば、音響製品の測定を目的とする無響室は、可聴帯域の音を主として吸収するように設計されています。一方、電波を発する通信機器のための電波無響室は、電磁波を吸収できるように内装が設計されています。
finalでは、より良い音響製品を開発するために、無響室での測定や試聴評価を頻繫に行っています。以前、final LAB Twitterで無響室に関する投稿をしましたが、今回は、無響室発展の歴史に着目したいと思います。無響室の歴史を振り返ると、無響室を使用する際に注意すべき重要なポイントを知ることができます。そして、無響室のことをもっと知っていただければ、音響製品の仕様や性能などの音響測定データを見ていただくときに、より身近に感じていただけると思います。音響製品を開発する私たちと、音響製品をお使いいただく皆様の双方で、無響室での測定がいかに重要かを理解していけば、音響製品に使用される技術のさらなる発展に繋がっていくものと信じています。
筆者が参照した文献の中で、無響室に関する最初の記述があるのは、1951年の文献です[1]。この文献が紹介しているのは、1928年の英国メトロポリタン・ヴィッカース電気会社(Metropolitan Vickers Electrical Company)の実験室でした。当時はまだ「無響室」という名称ではなく、「自由音場(Free field)に似せる実験室」と呼ばれていました。しかも、音響機器開発のためではなく、主に電気モーターなど機械騒音を測定する実験室として使用されていました。残念ながらこの最初の音響実験室の写真はありません。図2は、その音響実験室を1933年に増築した第二実験室です。
1936年、E. H. Bedellはベル研究所で自由音場を作り出すことを試みました[2]。複数の布を多層に重ねた平坦な吸音体サンプルを試作し、そのサンプルを垂直入射法(音響管法)で測定した結果、高い吸音率があることを確認しました。ただ、この吸音体を使用して完成した実験室の吸音率を実際に測定したところ、予想した吸音率より低いことが分かりました。当時は吸音体に対する音波の斜め入射を考慮していなかったため、こういった結果になったのだろうと思われます。
1940年、ドイツの学者Erwin Meyerは、初めて音響インピーダンスをマッチングする概念を発表しました[3]。つまり、吸音材と入射音の音響インピーダンスがうまくマッチングしないと反射が起こり、吸音効果が低下するということを発表したのです。この理論に基づき、彼はピラミッド状の吸音体を提案しました。さらに、吸音体の寸法と吸音率との関係も詳細に検討し(Parametric study)、吸音体の形状を最適化しました。こうして、ロックウールを充填した吸音体32000個を図3のように部屋の中に配置しました。この実験室において、被測定音源から3メートルの範囲の幾つかの測定点において音響測定した結果、各周波数帯域の音圧減衰予測値に対して測定結果が2 dB以内の偏差に収まっていることがわかり、十分な性能を有する音響実験室が完成したわけです。
1943年、アメリカの学者Leo L. Beranekは、第二次世界大戦中、政府からの依頼を受け、ハーバード大学で音響実験室を設計しました*[4]。彼は自由音場ということばを言い換え、「echo- free (Anechoic)」つまり「無響」ということばを初めて用いました。彼も音響インピーダンスマッチングの理論に基づき、吸音体の形状を実験で検討しました。また、Meyerが提案したピラミッド状の吸音体は製造と設置のコストが高いことを指摘し、くさび状のほうが効率的だと主張しました。さらに吸音効果を高めるため、吸音体の背後に空気層を設けることも提案しました。Beranekは逆二乗則の測定結果と、Meyerも使った減衰予測値の偏差値の測定結果をもとに、完成した無響室が十分な性能を有することを示しました。残念ながら、第二次世界大戦後、アメリカ政府は戦時に建造したものを取り壊すという目的で、ハーバード大学に二つの提案をしました。一つは、アメリカ政府が費用を負担し、すぐに取り壊すというものです。もう一つは、ハーバード大学が1ドルで無響室を買い取り、今後の運営費用は大学側が負担するというものです。当時のハーバード大学には無響室を利用する研究がなかったので、この無響室が撤去されてしまいました。[5]
*著作権により無響室の写真を掲載できませんが、興味がある方は、Googleでの検索でご覧いただけます([リンク])。
Beranekの研究成果に影響され、くさび状吸音体はほぼ無響室の標準仕様になっていきました。1947年にベル研究所もくさび状吸音体を使って、確認できる範囲でいえば、現存するなかで最古の無響室を建設しました**。
**著作権により無響室の写真を掲載できませんが、興味がある方は、Googleでの検索でご覧いただけます([リンク])。
くさびやピラミッド状の吸音体は音響インピーダンスマッチングの理論を利用したよい設計ではありますが、吸音体に関する研究は終ってはいません。最近の研究動向を以下ご紹介します。
一つめは、吸音体の形状の最適化です。くさび状吸音体の設計数式([リンク])では、下限周波数は吸音体の長さ(長さとはくさびの根本から先端までの距離を意味しますが、本文では、以降、長さを厚みと書き換えます。)にしか関係していませんが、実際はそれだけではありません。吸音体に用いる均質材の吸音特性と、吸音体の形状によって、音響インピーダンスが変化します。そして音響インピーダンスが入射音と吸音体でマッチングしない場合、吸音体の吸音性能が落ち、設計式から算出された下限周波数に、実際に吸音できる下限周波数が届きません。無響室の設計検討が始まった当時、材料技術が今ほど進歩していなかったため、使える吸音材は限られていました(均質材のロックウール、グラスファイバー、布など)。また、吸音材の音響特性も十分に把握できていなかったため、音響インピーダンスをマッチングさせるには、実験検証で適切な吸音体の形状を探すしかありませんでした。均質材で吸音体を作るのが最もコストが低いため、今でも、均質材による吸音体を用いるのが無響室の主流です。ただし当時と異なり、材料技術の進歩により、使える均質材は多様になり、例えば、よく使われるグラスウールでも密度を選べるようになりました。現在は32kg/m3、64 kg/m3、96 kg/m3などから選べます。あるいは安全性が高いポリエステル材も使えます。また、吸音材の研究も進んで、吸音材の音響特性をパラメーター化することもできるようになりました。加えて計算機や、シミュレーション技術も進化し、短時間にたくさんの吸音材と形状の組み合わせを検討することができるようになったため、材料や形状を最適化した吸音体を設計することが可能になりました。
二つめは、吸音体の薄型化です。Meyerが完成した無響室では、ピラミッド状吸音体が室内全容積のおよそ50%も占めていました[4]。この吸音体が膨大な容積を占める問題を解決するために、吸音体の厚みを薄くする研究がたくさん行われました。1963年、小林理学研究所の子安勝は吸音体の先端は弱くて、人や機材が接触したら破損する可能性があることを示しました。さらに、くさび状吸音体を先端からテーパの全長の30%までカットしても、吸音特性はほとんど変わらないことを実験で明らかにしました[6]。こうして無響室内の有効範囲をさらに広げることができました。現在、国内におけるくさび状吸音体を使っている無響室の吸音体がほぼ台形になっているのは、こういった研究があるからです。ちなみに、海外にはまだ先端がカットされていない無響室がたくさんあります。
さらに近年では、吸音のメカニズムに関する研究と材料技術のさらなる進化によって、多様な吸音構造や材料を組み合わせた吸音体も製造できるようになりました。この複層材料を利用して音響インピーダンスマッチングを検討することによって、くさび状吸音体より薄く、吸音性能も劣らないフラットな吸音体の開発に成功した研究が報告されています[7-8]。その一例が、図5に示した、ドイツのFAIST社による厚み350mm、下限周波数50Hzの吸音体です。
くさび状吸音体で反射音をなくした無響室の歴史は長く、これまでの研究の積み重ねで、その理論と設計手法も明確になりつつあります。ただし、くさび状吸音体の難点といえばその厚みです。下限周波数を低くするためには、かなり厚いくさび状吸音体を用いなければならず、その結果、無響室を作るためには、広い土地と空間が必要となります。しかしながら、複層材料による薄い吸音体が開発された結果、無響室建造に関する先決条件(床面積、室内空間容積)が緩和され、よりコンパクトな無響室の実現が可能になりました。さらに工場や会社などの室内に置くことも可能な、組み立て式で持ち運び可能な無響室や無響箱も開発されています。もちろん、こういった組み立て式無響室が吸音できる周波数帯域幅は、まだ従来の無響室より狭いです。しかしながら、こういった技術の研究開発がさらに進めば、今後、より小さな室内空間(例えば6畳の部屋)内にも、無響室を作ることができるようになるのではないかと期待しています。
参考文献
[1] A. Fleming, B. G. Churcher and L. J. Davies, “The research laboratories of Associated Electrical Industries Ltd.”, Proc. Roy. Soc. A, vol. 210, issue. 1101, pp. 145-172, 1951.
[2] E. H. Bedell, “Some Data on a Room Designed for Free Field Measurements”, J. Acoust. Soc. Am., vol. 8, pp. 118-125, 1936.
[3] E. Meyer, G. Buchmann and A. Schoch, “Ein neue Schallschluckanordnung hoher Wirksamkeit und der Bau eines schallgedämpften Raumes”, Akust. Z., vol. 5, pp. 352-364,1940.
[4] L. L. Beranek and H. P. Sleeper, “The design and construction of anechoic sound chambers”,J. Acoust. Soc. Am., vol. 18, no. 1, pp. 140-150, 1946.
[5] No Writer Attributed. (1971 March 30). Eerie Echoless Room Torn Down With Lab. The Harvard Crimson.
[6] 子安勝, “防音室・無響室・遮音室ー要求される性能と実現の方法についてー”, AUDIOLOGY, vol. 6, no. 4, pp. 269-277, 1963.
[7] J. F. Xu, J. M. Buchholz and F. R. Fricke, “Flat-walled multilayered anechoic linings: Optimization and application”, J. Acoust. Soc. Am., vol. 118, no. 5, pp. 3104-3109, 2005.
[8] Helmut V. Fuuchs, Xueqin Zha and Gerhard Babuke, “Broadband compact absorbers for anechoic linings”, CFA/DAGA, Strasbourg, 2004.
謝辞および著作権に関する説明
図2は参考文献[1]から引用し、Proceedings of the Royal Society Aの著作権ポリシーを遵守し写真掲載を行っています。https://royalsociety.org/journals/permissions/
図3は参考文献[3]から引用し、当文献はオープンアクセスになっており、こちらの[リンク]から閲覧できます。
Seki