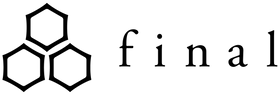音に関連した多様な分野で活躍される方々をお招きし、弊社チーフサイエンティストの濱﨑が、「音」についての様々なテーマについてお話を伺う企画です。第3回目は、オーディオ・ビジュアル評論家の麻倉怜士氏をお招きし、弊社社長の細尾も加わり、ZE8000を生み出した finalの音響 研究開発について、鼎談いたしました。パート1は、『定説を疑う』です。
↓ 下記より動画でもご覧いただけます。
麻倉:こんにちは。今日は大変楽しみにしておりました。私が最近聴いたオーディオ製品の中で、最も鮮烈な印象を受けたTWS(Truely Wireless Stereo、完全ワイヤレス)イヤホンのZE8000について、精魂を込めて作ったという細尾社長と、技術担当の濱﨑さんにお話をお伺いしたいと思います。時々常識は壊されて革新が起きることがありますが、ZE8000の登場はまさにそれが起きたではないかと思いました。
完全ワイヤレスイヤホンは、いろいろな制約があるので、これぐらいが良いところだよという妥協がありました。でも“これぐらい”というのは、これまでそうそうとして各社がハイエンドといわれるイヤホンを出してきたんだけれど、でも私に言わせると、これは? というのもたくさんありました。それらを聴いてきた中で、このZE8000を初めに聴いた瞬間びっくりしましたのです。本当の音楽を鳴らす音がここにあった。細尾社長、すごいものをお創りになりましたね。
細尾:ありがとうございます。Bluetoothイヤホンが出始めた頃から、私達もBluetoothのイヤホンを作ろうとして試作もしたんですが、なかなか良い音が出ない。この良い音が出ないのは、Bluetoothが圧縮だからという思い込みがあったんですね。
麻倉:一般常識では、まさにそうです。
細尾:ええ、私たちもそう思っていまして、どの商品を聴いてもBluetoothの音が聴こえると思っていたんです。ところが、開発をずっと続けている過程でBluetoothの音だと思っていたことは、もしかしたらそうではないのかもしれないと、あるところで気がついたんですね。
麻倉:その気付きはたいへん大きいですね。
業界はそれにはまだ気づいていません。Bluetoothの音が悪いというのを前提にして音作しているので、極端な方に行くのです。
細尾:そうなんです。あとは防水性能も重視されるので、開口(ベント)[1]が設けられなくなるので、低音がドンと出てしまうんです。低音がドンと出ると、どうしてもそれに合わせて高域を上げなければいけない。
麻倉:ドンシャリになります。
細尾:はい。私たちもそうした制約の中でやっていたので、Bluetoothを扱うのは難しいなと思っていたんです。そこで、一度その思い込みを全部取り払ってみようと。私たちが当たり前に正しいと思っていた定説を疑い出したのは、E3000を出したころでした。でも、はっきりとした形になっていなかったんですね。

麻倉:そういう常識への疑いの目は、常に持っていらっしゃると思うんですけども、特に今回強く出たということなのでしょうか?
細尾:そうです。私たちも当然いくつもの研究を並行していまして、その中でアコースティックの研究に関してはD8000やA8000に結実したのですが、それとは別にデジタル信号処理技術も研究していました。その各々が研究してきたことが一つに合わさったのがZE8000です。
麻倉:各々考えていた方向が、見渡してみると、同じ方向に行っているんじゃない! と気付いた。つまりBluetoothが決して悪いわけではないと。
細尾:そうです。Bluetoothは圧縮していますので、そこで発生している問題はコーデック[2]を開発したときに相当考えられているはずです。ですから、ある意味、優先順位で言うと一番上ではなかったということです。
麻倉:finalは“音とは何か?”というところをすごく詰めていらっしゃる。ヘッドホン、イヤホンに限らず、広い意味でのオーディオをね。そういうメーカーはあまりないんじゃないかと思うのです。そのfinalが結構強くストレスをかけて頑張っていたところ、一つの方向が出てきたということですね。
細尾:そうですね。基礎研究は時間やお金ばかり掛かって、結果が出せないという印象がありますよね。私たちも同じ問題に直面しそうになっていたのですが、人も少なくお金もなかったので、もう少し早くできる方法ないのか。最近の言葉でアジャイル開発[3]というのがありまして、その手法を活かして、もうちょっとコスパの良い基礎研究ができないかと。
麻倉:なるほど。普通、基礎研究は「ゆったりやってよ、待っているからさ」みたいな感じですよね(笑)
細尾:そうなんです。普通はエビデンスを積み重ねるので、なかなか終わらないのですが、いま私たちは何が必要かを逆算して、早いうちに商品的なものを試作してしまうというスタイルです。これに必要なのは、目利きとか編集力です。
麻倉:意味がわかっていないと、はたしてこの技術を研究して良いのか、わからないものね。
細尾:そうです。基礎研究の中でどういうものが本当に正しいのか、結論に至る早道はどこなのかを掴めるプロデューサー、編集者が必要です。それが濱﨑だと思っています。

麻倉:ここにいらっしゃる濱﨑さんは、私なんかとても近づけないというぐらいの方でして、なんとNHK放送技術研究所で、あの22.2チャンネルを開発された大エンジニアなのです。大変なオーディオの碩学で、論文もたくさん書いていらっしゃいます。そのような方をよくゲットできましたね(笑)。
細尾:おっしゃる通りです(笑)。私はデジタル信号処理について、本当に信じられるものなのかどうかがわからなくて、いろんな方にお話を聞いていました。その時、イヤホン、ヘッドホンではこんなことができるはずなんだ、とよく話していたので、そこをちょっと面白がっていただけたのかなと思っています。
麻倉:濱崎さん、どんなきっかけで、finalにジョインされたのですか?
濱﨑:きっかけは、私の先輩が経営する会社に、細尾からスピーカーの音をデジタル信号処理で補正するという依頼があったことです。 私自身ずっとプロ業界で働いてきたんですよね。音を作る、音を伝送する。そうしてユーザーさんに届けるところまではやってきたのですが、それを再生するコンシューマー業界に関してまったく経験がなかったのです。それがある時期から、どうやってユーザーさんがハイエンド・オーディオのスピーカーで聴いているかにとても興味を持ったんです。そこで、その先輩に仕事を手伝うので、どんな様子なのか見せてくださいとお願いしていました。
麻倉:そこで細尾社長のスピーカーから出た音を測って、それをデジタルフィルターで補正したと。
濱﨑:はい。ハイエンド・スピーカーをデジタル信号処理で音を良くする。この考え方は1985年頃だと思うのですが、当時、NHKでは最新鋭のデジタル信号処理で録音用のモニター・スピーカーを調整しようとしたんですね。でも、結局うまくいかなかった。それは厳しいのかなと思っていたら、先輩が「いまなら結構いけるよ」という話をしていて。
麻倉:当時とは技術がまったく違いますからね。
濱﨑:はい。40年経っていますからね。“本当にハイエンドの好きな人たちが、デジタル信号処理をした音を喜んでいるのかな?”と興味が湧いてきて、先輩と一緒にいろんなユーザーさんのところを回っていました。その中で、細尾からTADのスピーカーを調整してほしいということで、私もくっついて行って少し会話をした。それがきっかけです。
細尾:私もマニアとして“デジタル信号処理は、どこまでできるんだろう?”というのが知りたくて。そこで濱﨑にたくさん質問しても、的確にお答えいただけるので「おじさん、めちゃ詳しいですね」って。よくそんなことを言ったなって(笑)。
麻倉:正体知りませんからね(笑)。その経験を通して知見は得られたんですか?
濱﨑:一番大きかったのは、録音エンジニアの聴き方と、ユーザーさんの聴き方のポイントが違うことでした。プロのエンジニアは、左右のスピーカーの真ん中にどれだけきちっと音像定位するかがすごく大事なんです。プロはパンポットで音像定位位置を決めていくので、定位がきちっとわからないといけない。ところが、信号処理で音像定位を改善した後、多くのユーザーさんが、「定位は良いんだけど、音色は前の方が好きです」とおっしゃるのです。
スピーカーは複数のスピーカーユニット・オーディオ信号を分配するための帯域分割にLCネットワーク[4])を使っていますよね。当然クロスオーバー周波数
あたりで位相が非常に乱れるわけです。でも、その位相の乱れによって独特の音色感が生まれます。 それをきちっと直線位相に補正すると、その乱れがなくなってしまうので、確かに音像は良くなるけれど、音の広がり感が少し狭くなりスピーカーの間にきちっと入ってきます。 また音色において、歪みは必ずしも悪くはないんですよね。音に温かみがあるなどポジティブな印象を与えることがありますから。
麻倉:良い味になる。
濱﨑:そこをコンシューマーの人は見ているんだなと。
麻倉:とても面白い話ですね。コンシューマーにすると、プロはもう神様で、プロがやっているものがすべて正しいという一つのイメージがあります。だから、メーカーでも名前に“プロ”という名を付けるのはそういう効用があるからです。でも、じつはそうではないと。
濱﨑:はい。一番衝撃的だったのは、あるCDを取り出して「この音楽はうちのスピーカーだとうまく鳴らない」とおっしゃるんですね。その音源を聴いてみると録音が悪いんですよ。いまおっしゃったように、ユーザーさんは、録音は完璧で自分のスピーカーが悪いと思ってしまうのです。私が「これは録音が悪いので、もうちょっと良い録音の作品を探されたらどうですか?」というと、「録音が悪いはずはないじゃないですか」みたいな議論になっていく。
同じくイヤホン、ヘッドホンもユーザーさんを見ていると、やはり音が悪いと“イヤホンが悪い”という結論になりがちなのです。音を電気から音響に変換するトランスデューサー[5]に対する見方が、プロの録音エンジニアとコンシューマーでは見方がかなり違うんです。
麻倉:プロは経験を積んでいるし技術もあるから、これは音源の問題なのか、再生装置の問題なのか、すごく初期の段階で峻別しますよね。ところが、ユーザーさんは単なる音楽ファンであって、録音の良し悪しではなく、その音楽が好き嫌いで聴いているわけだから、一体どこに問題があるのかわかりづらい。
この問題は重要で、私もオーディオをチェックする際、そんなにたくさん聴かず、常に聴くのは3種類ぐらいにしているんです。そうすると音源はいつも同じなので、差分を聴いているわけで、悪さをしているのは、いったいどこにあるのか発見できます。

麻倉:さて、濱﨑さんはこの会社に入られて、ZE8000の開発で特にこだわったのはどういうところでしょうか。
濱﨑:開発当初から細尾と話をしていたのは“音色”ですね。音色にとにかくこだわったTWSイヤホンを作ってみたいということだったと思います。なぜTWSイヤホンなのかと言いますと、いままではアナログ信号を送ってトランスデューサーで音にするワイヤードと呼ぶジャンルは、音響工学的や機械音響的に、例えばフィルターを変えるとか、振動板の特性を変えるとか、あるいは振動板の後ろにある空気室の容積を変えて特性を整えていくことをしてきました。
麻倉:アコースティック関係ですね。
濱﨑:はい。アコースティックで理想的なものを作ろうとしても、そこに限界点があるんです。それがTWSイヤホンでは、アコースティックなところは、これまで積み重ねてきたfinalの技術がありますよね。そこにデジタル信号処理もパッケージで使える。それであれば、とことんやってみられる。それが音色という部分で結実して、これまでの概念とは違う、私たちはこう考えたんだという製品、ZE8000が作れたんじゃないかと思っています。
麻倉:いまオーディオの一つの潮流は、アクティブ・スピーカーです。従来はアンプがあって、ケーブルがあって、スピーカーがあると。それが、ここへ来て急にアクティブ・スピーカーが注目されてきた。つまりトータルな世界“アコースティック処理もあります”“マイクで測って信号処理で最適化できます”と、そのスピーカーを一番良く鳴らすことで音色を作っていく。考えてみると、確かにこれまでは従来のスピーカー的に鳴らすヘッドホンが一番良いというのが常識であって、それに対してTWSイヤホンは“Bluetoothだからね”みたいな感じで止まっていた。 いまのお話は、目からウロコですよ。どうしても上位概念がワイヤードで、TWSイヤホンはBluetoothという問題があるので、いくらアコースティック部分で頑張っても駄目じゃんというのがいままでは常識だった。そうじゃないということをfinalはZE8000で言った。これはすごいですね。コペルニクス的転回ですよ。
濱﨑:TWSイヤホンは、いまおっしゃったようにアクティブ・スピーカーと同じ概念ですよね。ワイヤレス信号を受信もできるし、受信した信号をデコードする機能もあるし、信号処理もあるし、アンプも内蔵していますし、ドライバーユニットも入っている。ですから、メーカー側で理想的なパッケージを作ることができる。アクティブ・スピーカーも同じように、メーカー側が必要な信号処理をしてパッケージする。あとはユーザーさんがそこに流すソースを選ぶ。
この流すソースについてはコーデックの問題があります。世の中はいま物理メディアからストリーミングへと至っているところで、おそらくコーデックについてはこれから本格的に議論をされていくと思っています。
いままでスピーカーにおいては、音質の問題はどこにあるかが、ちょっと混沌としていたと思うんですね。ケーブルなのか、アンプなのか、それともスピーカーの置き方なのか。アクティブ・スピーカーとしてパッケージで提供できれば、後はスピーカーを設置する部屋の室内音響か、あるいはソース側の問題に集約できますよね。 TWSイヤホンの世界もパッケージで最適化できれば、そこで初めてコーデックは何がいいのか、サンプリング周波数は何がよいのかなどを議論できます。おそらくそこまでまったく至っていなかった。それが、なんとなくBluetoothのロッシー・コーデックが悪いという概念で、音質論はそこで止まっていた。我々はただ原理原則に則って、まずパッケージで良い音を作りますというところをやってきて、やっと音質について議論のスタート地点に立ったと考えています。
麻倉:もの凄く面白いですね。その論法では音色を作るときに、パッシブだったら半分しか作れないわけです。プロオーディオの世界も、かつてはすごいアンプがあって、パッシブのモニター・スピーカーでやっていたんだけど、いまほとんどアクティブ・スピーカーじゃないですか。
濱﨑:そうですね。
麻倉:スピーカー・メーカーのGENELECに聞くと、非常にニュートラルな音を作るという目的のために、アクティブにしているといいます。そういう意味では、プロのオーディオの世界、そしてコンシューマーのハイエンドの世界が、段々アクティブに行くのは当然の流れです。イヤホンの世界も、これまではケーブルが付いていてアコースティックなもの、つまりパッシブだった。そこでは、音の半分はスマホであるとかDAPで決められてきたわけですよね。そうすると、いくらよい音をイヤホンで作ったとしても、音は足し算ですから、総合の音色はメーカーで考えた音ではない。
濱﨑:そうですね。
麻倉:TWSイヤホンについても、これまで音の悪さというのはすべてBluetoothに着せて、信号処理やアコースティックなどがもたらす音の問題を真面目に見た人がいなかったんじゃないかと思いますね。
濱﨑:振り返ってみると、私はイヤホンやヘッドホン製造の専門家じゃないんでしょうね。規定概念が何もないんですよ。
麻倉:なるほど、そういうことだ(笑)。
濱﨑:だから、“なぜ、これをしないの?”と思うことがたくさんありました。そこは面白かったですね。たぶん掘り起こせば、活用できることはまだまだある。私がイヤホン、ヘッドホンの製造技術について、あまり経験がなかったからゼロから取り組めたのだと思います。おそらくイヤホンやヘッドホンをずっと経験を積んでこられた方は、いろんなことをご存知なだけに、なかなか発想を変えるのが難しいと思うんですね。そういう意味で、イヤホン・ヘッドホン製品の開発の経験がなかったから“こうすれば音が良くなるんじゃないですか”ということを違和感なく言えた。たぶん常識からするとおかしなことをたくさん言っているんですけど。
麻倉:それはすごく重要ですよね。新しい方向に行くというのは、かならずしも昔からやっている人が新しい方向に行けるわけではない。それが良いと思ってやっているわけだから。でも、のっぺりと平らに見えているものでも、別の方向からライトを当てると、そこにある溝が見えてくる。
濱﨑:以前から細尾と「イヤホン・ヘッドホンってじつは基本的な研究をしているようで、まだまだやられていないよね」とよく話しています。かなり分厚いオーディオトランスデューサーの専門書でも、イヤホンに関しては10ページぐらいで、ほとんどがスピーカーに関する記述なのです。プロの業界でもスピーカーが第一であって、イヤホンやヘッドホンって、どちらかというと音をチェックするときに使うアクセサリー的な扱いなんですね。コンシューマーもこれまではスピーカーで聴くというのが当たり前だった。
それが、いまや多くの若い人たちはイヤホン、ヘッドホンが中心になってきました。そうするとスピーカーの視点からイヤホン、ヘッドホンを見るのではなく“イヤホン、ヘッドホンで何を聴いているのか?”という視点から見なければいけない時代になってきています。しかし、やられて来なかったことがいっぱいあるので、研究としても本当に新しいことばかりの宝の山だと思います。

>>続きを見る:Part 2『犯人は接着剤?!』
ベントとはventすなわち通気孔のことです。通風孔もventと呼ばれています。イヤホンでは、イヤホンに取り付けられた通気孔をベントと呼んでおり、ダイナミック型ドライバーを採用したイヤホンに取り付けられていることが多い。ベントを採用するうえでの音質に対する目的は、イヤホンを耳に装着した際に、主として低域の音響特性を最適化するためです。ベントによって低域のブーストが適切に抑えられ、低域過多の音質になることを軽減する効果があります。音質以外では、外耳道が完全に閉塞されることによる違和感を少し和らげる効果もあります。
[2]コーデック
コーデック(Codec)とは、デジタルデータを圧縮または変換するための技術やアルゴリズムのことです。コーデックは、音声や映像などの多種多様なデータを、より小さなサイズに圧縮して、データの転送やストレージに利用しやすくします。デジタルデータを圧縮するプロセスをエンコード、そして元のデータに戻すためのプロセスをデコードと呼びます。 オーディオ信号のコーデックでは、元の信号を物理的に完全に復元できるものをロスレスコーデック(Lossless codec)、元の信号を物理的に完全に復元できないものをロッシーコーデック(Lossy codec)と呼んでいます。後者はヒトの聴覚特性を利用して、元のオーディオ信号と聞こえが極力変化しないようにデータを圧縮する技術が利用されているケースが多いようです。 TWSイヤホン等で利用されているBluetoothによるオーディオ信号伝送では、コーデックが必要になります。Bluetoothのオーディオコーデックは、オーディオ信号をデジタルデータに変換し、Bluetooth接続によって対象となるデバイスに送信するために用いられます。受信側では、受信したデータをデコードし、元のオーディオ信号に復元します。 Bluetoothのオーディオコーデックには、いくつかの種類があります。例えば、SBC(Subband Coding)、AAC(Advanced Audio Coding)、aptX、LDAC(Low Delay Audio Codec)などがあります。SBCは、Bluetoothによるオーディオ伝送の基本的なコーデックで、ほとんどのBluetooth対応のデバイスでサポートされています。AACは、より高品質のオーディオ伝送を実現することができ、AppleのiOSデバイスでは標準的なコーデックとして使用されています。各デバイスでどのコーデックが利用できるかは、そのデバイスの仕様によって異なります。一般のBluetoothデバイスでは、サポートしているコーデックを自動的に選択し、最高品質のオーディオ伝送を実現するようになっています。
[3]アジャイル開発
アジャイル開発とは、ソフトウェア開発のプロセスであり、従来の開発プロセスとは異なる手法です。アジャイル開発では、顧客と開発チームが密接に連携して、継続的な改善を行い、より高品質なソフトウェアを迅速かつ柔軟に開発することが目的とされています。 アジャイル開発の特徴としては、開発作業を短い期間に区切り、期間ごとにリリース可能な状態にすることを目指します。そして、顧客のニーズや環境の変化に対応できるように、開発プロセスやソフトウェアの変更が容易にできるようになっています。そのうえで、開発チームは、継続的な改善を行いながら、品質を向上させていきます。 アジャイル開発の利点としては、開発期間の短縮や品質の向上や顧客満足度の向上などが挙げられます。ただしこういった利点を活かすためには、アジャイル開発では、適切なプロジェクト管理が必須となります。
[4]LCネットワーク
LCネットワークは、ウーファー、スコーカー、ツィーター等の複数の異なるスピーカーユニットで構成されるスピーカーにおいて、各スピーカーユニットに対して最適になるように、入力されるオーディオ信号を複数の帯域に分割するために利用されます。 LCネットワークは、コイル(L)とキャパシタ(C)を組み合わせたアナログ回路のことを指します。この回路は、LとCの値を設計することにより特定の周波数帯域の信号を通過させることができます。 スピーカーにおいて、使用されるスピーカーユニット毎に最適な帯域に分割する回路をクロスオーバー回路と呼び、LCネットワークはこのクロスオーバー回路に用いられています。 最近では、デジタルオーディオ信号処理を利用したクロスオーバー回路を内蔵したスピーカーや、デジタルオーディオ信号処理を利用したクロスオーバー機能を持つ単独のオーディオ機器も発売されています。
[5]トランスデューサー
トランスデューサーとは、音波を電気信号に変換する、あるいは、電気信号を音波に変換する電気音響変換デバイスのことです。前者はマイクロホンなどがあり、後者はスピーカー、イヤホン、ヘッドホンなどがあります。 音波を扱うオーディオ技術にとっては特に重要なデバイスがトランスデューサーです。トランスデューサー以外のオーディオ機器はデジタルオーディオ信号処理技術の発達とともに大きく変化をしてきましたが、トランスデューサーは、改良により音質の改善がなされてきたものの、基本的には従来技術が現在もベースとなっています。 現在市場に出ているトランスデューサーを利用した製品の多くは、電気音響変換のために振動板を利用しています。レーザー技術や熱音響技術を利用した振動板が不要なトランスデューサーも研究されてはいますが、実用的な製品となるにはまだいくつかの研究課題をクリアする必要があると思われます。
↓ 下記より動画でもご覧いただけます。
麻倉:こんにちは。今日は大変楽しみにしておりました。私が最近聴いたオーディオ製品の中で、最も鮮烈な印象を受けたTWS(Truely Wireless Stereo、完全ワイヤレス)イヤホンのZE8000について、精魂を込めて作ったという細尾社長と、技術担当の濱﨑さんにお話をお伺いしたいと思います。時々常識は壊されて革新が起きることがありますが、ZE8000の登場はまさにそれが起きたではないかと思いました。
完全ワイヤレスイヤホンは、いろいろな制約があるので、これぐらいが良いところだよという妥協がありました。でも“これぐらい”というのは、これまでそうそうとして各社がハイエンドといわれるイヤホンを出してきたんだけれど、でも私に言わせると、これは? というのもたくさんありました。それらを聴いてきた中で、このZE8000を初めに聴いた瞬間びっくりしましたのです。本当の音楽を鳴らす音がここにあった。細尾社長、すごいものをお創りになりましたね。
細尾:ありがとうございます。Bluetoothイヤホンが出始めた頃から、私達もBluetoothのイヤホンを作ろうとして試作もしたんですが、なかなか良い音が出ない。この良い音が出ないのは、Bluetoothが圧縮だからという思い込みがあったんですね。
麻倉:一般常識では、まさにそうです。
細尾:ええ、私たちもそう思っていまして、どの商品を聴いてもBluetoothの音が聴こえると思っていたんです。ところが、開発をずっと続けている過程でBluetoothの音だと思っていたことは、もしかしたらそうではないのかもしれないと、あるところで気がついたんですね。
麻倉:その気付きはたいへん大きいですね。
業界はそれにはまだ気づいていません。Bluetoothの音が悪いというのを前提にして音作しているので、極端な方に行くのです。
細尾:そうなんです。あとは防水性能も重視されるので、開口(ベント)[1]が設けられなくなるので、低音がドンと出てしまうんです。低音がドンと出ると、どうしてもそれに合わせて高域を上げなければいけない。
麻倉:ドンシャリになります。
細尾:はい。私たちもそうした制約の中でやっていたので、Bluetoothを扱うのは難しいなと思っていたんです。そこで、一度その思い込みを全部取り払ってみようと。私たちが当たり前に正しいと思っていた定説を疑い出したのは、E3000を出したころでした。でも、はっきりとした形になっていなかったんですね。

麻倉:そういう常識への疑いの目は、常に持っていらっしゃると思うんですけども、特に今回強く出たということなのでしょうか?
細尾:そうです。私たちも当然いくつもの研究を並行していまして、その中でアコースティックの研究に関してはD8000やA8000に結実したのですが、それとは別にデジタル信号処理技術も研究していました。その各々が研究してきたことが一つに合わさったのがZE8000です。
麻倉:各々考えていた方向が、見渡してみると、同じ方向に行っているんじゃない! と気付いた。つまりBluetoothが決して悪いわけではないと。
細尾:そうです。Bluetoothは圧縮していますので、そこで発生している問題はコーデック[2]を開発したときに相当考えられているはずです。ですから、ある意味、優先順位で言うと一番上ではなかったということです。
麻倉:finalは“音とは何か?”というところをすごく詰めていらっしゃる。ヘッドホン、イヤホンに限らず、広い意味でのオーディオをね。そういうメーカーはあまりないんじゃないかと思うのです。そのfinalが結構強くストレスをかけて頑張っていたところ、一つの方向が出てきたということですね。
細尾:そうですね。基礎研究は時間やお金ばかり掛かって、結果が出せないという印象がありますよね。私たちも同じ問題に直面しそうになっていたのですが、人も少なくお金もなかったので、もう少し早くできる方法ないのか。最近の言葉でアジャイル開発[3]というのがありまして、その手法を活かして、もうちょっとコスパの良い基礎研究ができないかと。
麻倉:なるほど。普通、基礎研究は「ゆったりやってよ、待っているからさ」みたいな感じですよね(笑)
細尾:そうなんです。普通はエビデンスを積み重ねるので、なかなか終わらないのですが、いま私たちは何が必要かを逆算して、早いうちに商品的なものを試作してしまうというスタイルです。これに必要なのは、目利きとか編集力です。
麻倉:意味がわかっていないと、はたしてこの技術を研究して良いのか、わからないものね。
細尾:そうです。基礎研究の中でどういうものが本当に正しいのか、結論に至る早道はどこなのかを掴めるプロデューサー、編集者が必要です。それが濱﨑だと思っています。

麻倉:ここにいらっしゃる濱﨑さんは、私なんかとても近づけないというぐらいの方でして、なんとNHK放送技術研究所で、あの22.2チャンネルを開発された大エンジニアなのです。大変なオーディオの碩学で、論文もたくさん書いていらっしゃいます。そのような方をよくゲットできましたね(笑)。
細尾:おっしゃる通りです(笑)。私はデジタル信号処理について、本当に信じられるものなのかどうかがわからなくて、いろんな方にお話を聞いていました。その時、イヤホン、ヘッドホンではこんなことができるはずなんだ、とよく話していたので、そこをちょっと面白がっていただけたのかなと思っています。
麻倉:濱崎さん、どんなきっかけで、finalにジョインされたのですか?
濱﨑:きっかけは、私の先輩が経営する会社に、細尾からスピーカーの音をデジタル信号処理で補正するという依頼があったことです。 私自身ずっとプロ業界で働いてきたんですよね。音を作る、音を伝送する。そうしてユーザーさんに届けるところまではやってきたのですが、それを再生するコンシューマー業界に関してまったく経験がなかったのです。それがある時期から、どうやってユーザーさんがハイエンド・オーディオのスピーカーで聴いているかにとても興味を持ったんです。そこで、その先輩に仕事を手伝うので、どんな様子なのか見せてくださいとお願いしていました。
麻倉:そこで細尾社長のスピーカーから出た音を測って、それをデジタルフィルターで補正したと。
濱﨑:はい。ハイエンド・スピーカーをデジタル信号処理で音を良くする。この考え方は1985年頃だと思うのですが、当時、NHKでは最新鋭のデジタル信号処理で録音用のモニター・スピーカーを調整しようとしたんですね。でも、結局うまくいかなかった。それは厳しいのかなと思っていたら、先輩が「いまなら結構いけるよ」という話をしていて。
麻倉:当時とは技術がまったく違いますからね。
濱﨑:はい。40年経っていますからね。“本当にハイエンドの好きな人たちが、デジタル信号処理をした音を喜んでいるのかな?”と興味が湧いてきて、先輩と一緒にいろんなユーザーさんのところを回っていました。その中で、細尾からTADのスピーカーを調整してほしいということで、私もくっついて行って少し会話をした。それがきっかけです。
細尾:私もマニアとして“デジタル信号処理は、どこまでできるんだろう?”というのが知りたくて。そこで濱﨑にたくさん質問しても、的確にお答えいただけるので「おじさん、めちゃ詳しいですね」って。よくそんなことを言ったなって(笑)。
麻倉:正体知りませんからね(笑)。その経験を通して知見は得られたんですか?
濱﨑:一番大きかったのは、録音エンジニアの聴き方と、ユーザーさんの聴き方のポイントが違うことでした。プロのエンジニアは、左右のスピーカーの真ん中にどれだけきちっと音像定位するかがすごく大事なんです。プロはパンポットで音像定位位置を決めていくので、定位がきちっとわからないといけない。ところが、信号処理で音像定位を改善した後、多くのユーザーさんが、「定位は良いんだけど、音色は前の方が好きです」とおっしゃるのです。
スピーカーは複数のスピーカーユニット・オーディオ信号を分配するための帯域分割にLCネットワーク[4])を使っていますよね。当然クロスオーバー周波数
あたりで位相が非常に乱れるわけです。でも、その位相の乱れによって独特の音色感が生まれます。 それをきちっと直線位相に補正すると、その乱れがなくなってしまうので、確かに音像は良くなるけれど、音の広がり感が少し狭くなりスピーカーの間にきちっと入ってきます。 また音色において、歪みは必ずしも悪くはないんですよね。音に温かみがあるなどポジティブな印象を与えることがありますから。
麻倉:良い味になる。
濱﨑:そこをコンシューマーの人は見ているんだなと。
麻倉:とても面白い話ですね。コンシューマーにすると、プロはもう神様で、プロがやっているものがすべて正しいという一つのイメージがあります。だから、メーカーでも名前に“プロ”という名を付けるのはそういう効用があるからです。でも、じつはそうではないと。
濱﨑:はい。一番衝撃的だったのは、あるCDを取り出して「この音楽はうちのスピーカーだとうまく鳴らない」とおっしゃるんですね。その音源を聴いてみると録音が悪いんですよ。いまおっしゃったように、ユーザーさんは、録音は完璧で自分のスピーカーが悪いと思ってしまうのです。私が「これは録音が悪いので、もうちょっと良い録音の作品を探されたらどうですか?」というと、「録音が悪いはずはないじゃないですか」みたいな議論になっていく。
同じくイヤホン、ヘッドホンもユーザーさんを見ていると、やはり音が悪いと“イヤホンが悪い”という結論になりがちなのです。音を電気から音響に変換するトランスデューサー[5]に対する見方が、プロの録音エンジニアとコンシューマーでは見方がかなり違うんです。
麻倉:プロは経験を積んでいるし技術もあるから、これは音源の問題なのか、再生装置の問題なのか、すごく初期の段階で峻別しますよね。ところが、ユーザーさんは単なる音楽ファンであって、録音の良し悪しではなく、その音楽が好き嫌いで聴いているわけだから、一体どこに問題があるのかわかりづらい。
この問題は重要で、私もオーディオをチェックする際、そんなにたくさん聴かず、常に聴くのは3種類ぐらいにしているんです。そうすると音源はいつも同じなので、差分を聴いているわけで、悪さをしているのは、いったいどこにあるのか発見できます。

濱﨑:開発当初から細尾と話をしていたのは“音色”ですね。音色にとにかくこだわったTWSイヤホンを作ってみたいということだったと思います。なぜTWSイヤホンなのかと言いますと、いままではアナログ信号を送ってトランスデューサーで音にするワイヤードと呼ぶジャンルは、音響工学的や機械音響的に、例えばフィルターを変えるとか、振動板の特性を変えるとか、あるいは振動板の後ろにある空気室の容積を変えて特性を整えていくことをしてきました。
麻倉:アコースティック関係ですね。
濱﨑:はい。アコースティックで理想的なものを作ろうとしても、そこに限界点があるんです。それがTWSイヤホンでは、アコースティックなところは、これまで積み重ねてきたfinalの技術がありますよね。そこにデジタル信号処理もパッケージで使える。それであれば、とことんやってみられる。それが音色という部分で結実して、これまでの概念とは違う、私たちはこう考えたんだという製品、ZE8000が作れたんじゃないかと思っています。
麻倉:いまオーディオの一つの潮流は、アクティブ・スピーカーです。従来はアンプがあって、ケーブルがあって、スピーカーがあると。それが、ここへ来て急にアクティブ・スピーカーが注目されてきた。つまりトータルな世界“アコースティック処理もあります”“マイクで測って信号処理で最適化できます”と、そのスピーカーを一番良く鳴らすことで音色を作っていく。考えてみると、確かにこれまでは従来のスピーカー的に鳴らすヘッドホンが一番良いというのが常識であって、それに対してTWSイヤホンは“Bluetoothだからね”みたいな感じで止まっていた。 いまのお話は、目からウロコですよ。どうしても上位概念がワイヤードで、TWSイヤホンはBluetoothという問題があるので、いくらアコースティック部分で頑張っても駄目じゃんというのがいままでは常識だった。そうじゃないということをfinalはZE8000で言った。これはすごいですね。コペルニクス的転回ですよ。
濱﨑:TWSイヤホンは、いまおっしゃったようにアクティブ・スピーカーと同じ概念ですよね。ワイヤレス信号を受信もできるし、受信した信号をデコードする機能もあるし、信号処理もあるし、アンプも内蔵していますし、ドライバーユニットも入っている。ですから、メーカー側で理想的なパッケージを作ることができる。アクティブ・スピーカーも同じように、メーカー側が必要な信号処理をしてパッケージする。あとはユーザーさんがそこに流すソースを選ぶ。
この流すソースについてはコーデックの問題があります。世の中はいま物理メディアからストリーミングへと至っているところで、おそらくコーデックについてはこれから本格的に議論をされていくと思っています。
いままでスピーカーにおいては、音質の問題はどこにあるかが、ちょっと混沌としていたと思うんですね。ケーブルなのか、アンプなのか、それともスピーカーの置き方なのか。アクティブ・スピーカーとしてパッケージで提供できれば、後はスピーカーを設置する部屋の室内音響か、あるいはソース側の問題に集約できますよね。 TWSイヤホンの世界もパッケージで最適化できれば、そこで初めてコーデックは何がいいのか、サンプリング周波数は何がよいのかなどを議論できます。おそらくそこまでまったく至っていなかった。それが、なんとなくBluetoothのロッシー・コーデックが悪いという概念で、音質論はそこで止まっていた。我々はただ原理原則に則って、まずパッケージで良い音を作りますというところをやってきて、やっと音質について議論のスタート地点に立ったと考えています。
麻倉:もの凄く面白いですね。その論法では音色を作るときに、パッシブだったら半分しか作れないわけです。プロオーディオの世界も、かつてはすごいアンプがあって、パッシブのモニター・スピーカーでやっていたんだけど、いまほとんどアクティブ・スピーカーじゃないですか。
濱﨑:そうですね。
麻倉:スピーカー・メーカーのGENELECに聞くと、非常にニュートラルな音を作るという目的のために、アクティブにしているといいます。そういう意味では、プロのオーディオの世界、そしてコンシューマーのハイエンドの世界が、段々アクティブに行くのは当然の流れです。イヤホンの世界も、これまではケーブルが付いていてアコースティックなもの、つまりパッシブだった。そこでは、音の半分はスマホであるとかDAPで決められてきたわけですよね。そうすると、いくらよい音をイヤホンで作ったとしても、音は足し算ですから、総合の音色はメーカーで考えた音ではない。
濱﨑:そうですね。
麻倉:TWSイヤホンについても、これまで音の悪さというのはすべてBluetoothに着せて、信号処理やアコースティックなどがもたらす音の問題を真面目に見た人がいなかったんじゃないかと思いますね。
濱﨑:振り返ってみると、私はイヤホンやヘッドホン製造の専門家じゃないんでしょうね。規定概念が何もないんですよ。
麻倉:なるほど、そういうことだ(笑)。
濱﨑:だから、“なぜ、これをしないの?”と思うことがたくさんありました。そこは面白かったですね。たぶん掘り起こせば、活用できることはまだまだある。私がイヤホン、ヘッドホンの製造技術について、あまり経験がなかったからゼロから取り組めたのだと思います。おそらくイヤホンやヘッドホンをずっと経験を積んでこられた方は、いろんなことをご存知なだけに、なかなか発想を変えるのが難しいと思うんですね。そういう意味で、イヤホン・ヘッドホン製品の開発の経験がなかったから“こうすれば音が良くなるんじゃないですか”ということを違和感なく言えた。たぶん常識からするとおかしなことをたくさん言っているんですけど。
麻倉:それはすごく重要ですよね。新しい方向に行くというのは、かならずしも昔からやっている人が新しい方向に行けるわけではない。それが良いと思ってやっているわけだから。でも、のっぺりと平らに見えているものでも、別の方向からライトを当てると、そこにある溝が見えてくる。
濱﨑:以前から細尾と「イヤホン・ヘッドホンってじつは基本的な研究をしているようで、まだまだやられていないよね」とよく話しています。かなり分厚いオーディオトランスデューサーの専門書でも、イヤホンに関しては10ページぐらいで、ほとんどがスピーカーに関する記述なのです。プロの業界でもスピーカーが第一であって、イヤホンやヘッドホンって、どちらかというと音をチェックするときに使うアクセサリー的な扱いなんですね。コンシューマーもこれまではスピーカーで聴くというのが当たり前だった。
それが、いまや多くの若い人たちはイヤホン、ヘッドホンが中心になってきました。そうするとスピーカーの視点からイヤホン、ヘッドホンを見るのではなく“イヤホン、ヘッドホンで何を聴いているのか?”という視点から見なければいけない時代になってきています。しかし、やられて来なかったことがいっぱいあるので、研究としても本当に新しいことばかりの宝の山だと思います。

>>続きを見る:Part 2『犯人は接着剤?!』
用語解説
[1]ベントベントとはventすなわち通気孔のことです。通風孔もventと呼ばれています。イヤホンでは、イヤホンに取り付けられた通気孔をベントと呼んでおり、ダイナミック型ドライバーを採用したイヤホンに取り付けられていることが多い。ベントを採用するうえでの音質に対する目的は、イヤホンを耳に装着した際に、主として低域の音響特性を最適化するためです。ベントによって低域のブーストが適切に抑えられ、低域過多の音質になることを軽減する効果があります。音質以外では、外耳道が完全に閉塞されることによる違和感を少し和らげる効果もあります。
[2]コーデック
コーデック(Codec)とは、デジタルデータを圧縮または変換するための技術やアルゴリズムのことです。コーデックは、音声や映像などの多種多様なデータを、より小さなサイズに圧縮して、データの転送やストレージに利用しやすくします。デジタルデータを圧縮するプロセスをエンコード、そして元のデータに戻すためのプロセスをデコードと呼びます。 オーディオ信号のコーデックでは、元の信号を物理的に完全に復元できるものをロスレスコーデック(Lossless codec)、元の信号を物理的に完全に復元できないものをロッシーコーデック(Lossy codec)と呼んでいます。後者はヒトの聴覚特性を利用して、元のオーディオ信号と聞こえが極力変化しないようにデータを圧縮する技術が利用されているケースが多いようです。 TWSイヤホン等で利用されているBluetoothによるオーディオ信号伝送では、コーデックが必要になります。Bluetoothのオーディオコーデックは、オーディオ信号をデジタルデータに変換し、Bluetooth接続によって対象となるデバイスに送信するために用いられます。受信側では、受信したデータをデコードし、元のオーディオ信号に復元します。 Bluetoothのオーディオコーデックには、いくつかの種類があります。例えば、SBC(Subband Coding)、AAC(Advanced Audio Coding)、aptX、LDAC(Low Delay Audio Codec)などがあります。SBCは、Bluetoothによるオーディオ伝送の基本的なコーデックで、ほとんどのBluetooth対応のデバイスでサポートされています。AACは、より高品質のオーディオ伝送を実現することができ、AppleのiOSデバイスでは標準的なコーデックとして使用されています。各デバイスでどのコーデックが利用できるかは、そのデバイスの仕様によって異なります。一般のBluetoothデバイスでは、サポートしているコーデックを自動的に選択し、最高品質のオーディオ伝送を実現するようになっています。
[3]アジャイル開発
アジャイル開発とは、ソフトウェア開発のプロセスであり、従来の開発プロセスとは異なる手法です。アジャイル開発では、顧客と開発チームが密接に連携して、継続的な改善を行い、より高品質なソフトウェアを迅速かつ柔軟に開発することが目的とされています。 アジャイル開発の特徴としては、開発作業を短い期間に区切り、期間ごとにリリース可能な状態にすることを目指します。そして、顧客のニーズや環境の変化に対応できるように、開発プロセスやソフトウェアの変更が容易にできるようになっています。そのうえで、開発チームは、継続的な改善を行いながら、品質を向上させていきます。 アジャイル開発の利点としては、開発期間の短縮や品質の向上や顧客満足度の向上などが挙げられます。ただしこういった利点を活かすためには、アジャイル開発では、適切なプロジェクト管理が必須となります。
[4]LCネットワーク
LCネットワークは、ウーファー、スコーカー、ツィーター等の複数の異なるスピーカーユニットで構成されるスピーカーにおいて、各スピーカーユニットに対して最適になるように、入力されるオーディオ信号を複数の帯域に分割するために利用されます。 LCネットワークは、コイル(L)とキャパシタ(C)を組み合わせたアナログ回路のことを指します。この回路は、LとCの値を設計することにより特定の周波数帯域の信号を通過させることができます。 スピーカーにおいて、使用されるスピーカーユニット毎に最適な帯域に分割する回路をクロスオーバー回路と呼び、LCネットワークはこのクロスオーバー回路に用いられています。 最近では、デジタルオーディオ信号処理を利用したクロスオーバー回路を内蔵したスピーカーや、デジタルオーディオ信号処理を利用したクロスオーバー機能を持つ単独のオーディオ機器も発売されています。
[5]トランスデューサー
トランスデューサーとは、音波を電気信号に変換する、あるいは、電気信号を音波に変換する電気音響変換デバイスのことです。前者はマイクロホンなどがあり、後者はスピーカー、イヤホン、ヘッドホンなどがあります。 音波を扱うオーディオ技術にとっては特に重要なデバイスがトランスデューサーです。トランスデューサー以外のオーディオ機器はデジタルオーディオ信号処理技術の発達とともに大きく変化をしてきましたが、トランスデューサーは、改良により音質の改善がなされてきたものの、基本的には従来技術が現在もベースとなっています。 現在市場に出ているトランスデューサーを利用した製品の多くは、電気音響変換のために振動板を利用しています。レーザー技術や熱音響技術を利用した振動板が不要なトランスデューサーも研究されてはいますが、実用的な製品となるにはまだいくつかの研究課題をクリアする必要があると思われます。